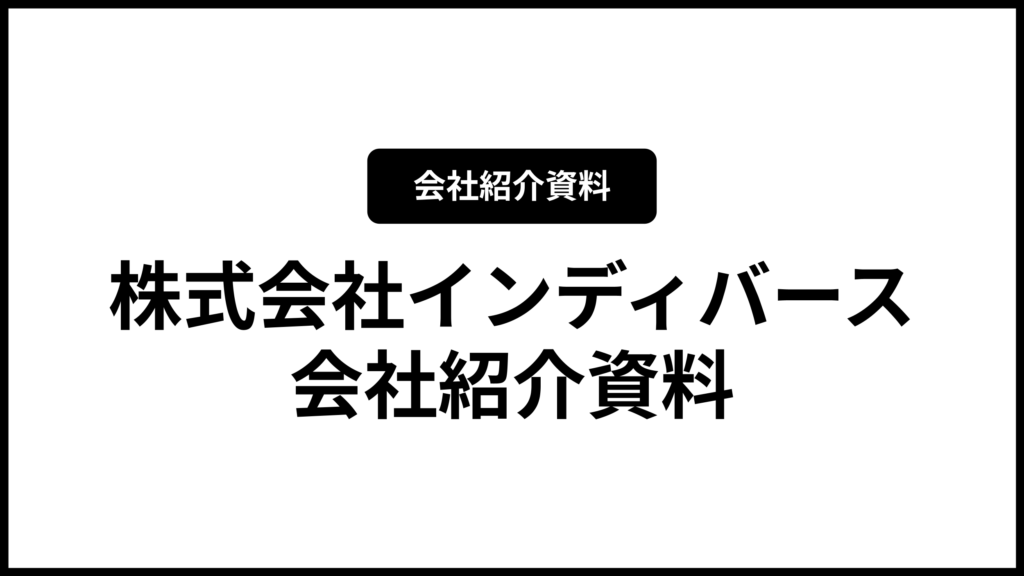SaaS企業にとってSEO(検索エンジン最適化)は、安定的なリード獲得チャネルになります。
広告に頼らず安定した見込み客を集められるため、マーケティングの費用対効果を高められます。
一方で、SaaSのオウンドメディアで成果を出すためには、いくつかの避けるべき落とし穴があります。
本記事では、実際にSaaS企業のSEO対策をご支援している経験から、成果を出す具体的な方法や戦略について解説します。
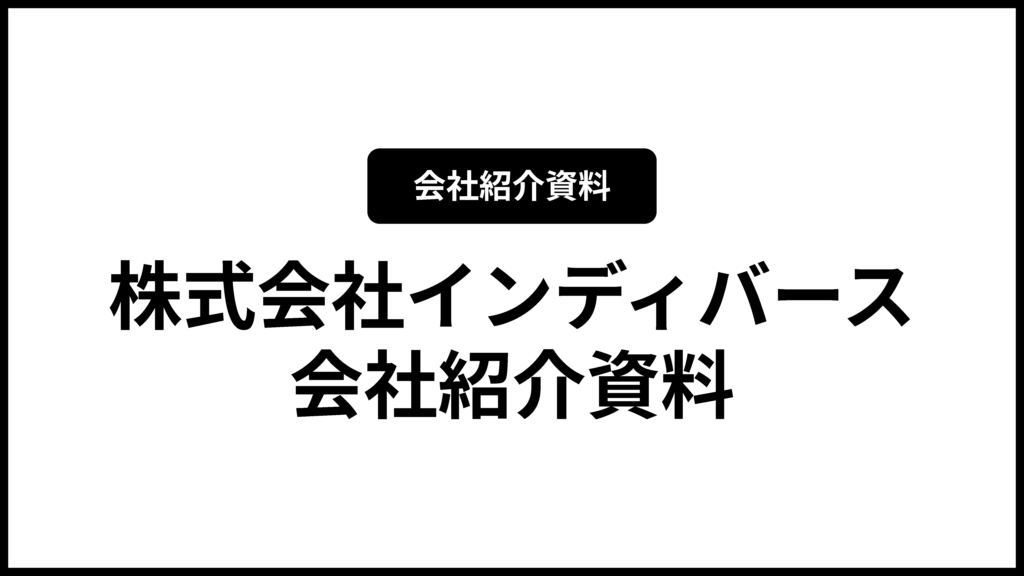
SEO施策全般にお困りの方へ
貴社のSEO施策全般の戦略立案から、実行までトータルサポート。
SEOコンサルティング/記事制作 / リライト/被リンク営業代行/Webアプリケーション開発 / 生成AI活用など、幅広く対応可能です。
SaaS企業におけるSEOのメリット
SaaS企業におけるSEOのメリットは以下のとおりです。
- リード獲得数の増加
- Paidマーケティングと比較して、CPAを下げやすい
順に解説します。
1. リード獲得数の増加
SaaS製品は基本的にオンラインで提供されるため、見込み顧客(リード)の多くは検索経由でサービスを探しています。
SEOによって自社サービスが検索結果の上位に表示されれば、広告以外のチャネルからも安定してコンバージョン(問い合わせや資料請求、トライアル申し込みなど)を獲得できます。
特にB2B SaaSでは、検索エンジン経由のリードはニーズが顕在化していることが多く、質が高い傾向があります。実際、多くの企業サイトではオーガニック検索からの流入が全体の半分以上を占めており、SEO経由の顧客獲得は事業拡大に不可欠です。
また優れたコンテンツを蓄積するほど効果が持続するため、一度上位表示を獲得できればその後も継続的にリードを生み出せます。
2. Paidマーケティングと比較して、CPAを下げやすい
広告(リスティングやSNS広告など)による集客は即効性がありますが、クリックや表示のたびにコストが発生し続けます。
それに対しSEOは、最初にコンテンツ作成やサイト改善に投資すれば、後は継続的に無料で流入を獲得できる点で優れています。
オーガニック検索で上位表示され続ける限り、追加コストなしに新たなユーザーが訪れるため、顧客獲得単価(CPA)を長期的に低く抑えられます。例えば、一度公開した記事コンテンツは何度も再利用・更新が可能で、半永久的に集客資産として機能します。
一方で広告は出稿を止めればパタリと流入が止まってしまいます。実際、SEO経由のユーザー獲得コストは総じて広告より低く、オーガニック流入が増えるほど追加の獲得コストは逓減していくとされています
以上の理由から、SaaS企業がマーケティングROIを最大化するにはSEOが効果的なのです。
SaaS企業のSEO対策方針
SaaS企業がSEOを進める際には、大きく分けて
- サービスページ(製品サイト)の最適化
- オウンドメディア(ブログなど)の運用
という2つの方針があります。
1. サービスページの対策
自社サイト内のサービス紹介ページや機能説明ページは、SaaS企業の「顔」となる重要ページです。
ここで狙うべきは自社サービス名やカテゴリ名などの単一キーワードでの上位表示です。具体的には、タイトルタグにサービス名+主要キーワードを含めることで、検索エンジンにページ内容を明確に伝えます。
例えばですが、以下の観点を見ていくとよいでしょう。
- サービス名で検索した時に、該当のページが表示されているか。
- Google Search Consoleなどで、サービス名とのかけあわせキーワードで検索されているキーワードに答えられるコンテンツがあるか。(例:料金 / トライアル / 使い方 / マニュアル等)
2. 導入事例を増やす
直接的にSEOで流入が増えるわけではありませんが、SEOで認知したユーザーがコンバージョンする上で非常に重要になってきます。
そのため、サービスの特徴や料金だけでなく、導入事例やお客様の声を充実させることも重要です。
3. 機能紹介ページを増やす
さらに、ユーザーが知りたい詳細情報に応えるために、目的別や機能別にサービス詳細ページを増やすのも有効です。例えば
- 「料金プラン」
- 「活用シーン」
など専用ページを設け、関連キーワードでの流入機会を広げます。
オウンドメディアの対策
サービスページで拾いきれない潜在顧客層にアプローチするには、オウンドメディア(自社ブログやナレッジベース)の活用が効果的です。
ここではユーザーが抱える課題や悩みに対して役立つ記事を制作し、関連キーワードで検索流入を狙います。
具体的な方針について共有します。
1. まずはイニシャルで記事を30~100本程度入れる
オウンドメディアに着手する場合、最低でも30記事ほど入れるとよいでしょう。Googleのアルゴリズムでは、ある特定のテーマに対してのサイトの情報網羅性が重要視されます。そのため、立ち上げの際には30記事ほど入れた上で、様子を見ていく形がよいでしょう。
2. CTAを追加する
記事内には無料トライアルや資料ダウンロードへのCTA(Call To Action)を設置し、読者がスムーズにコンバージョンできる動線を整えましょう。
- 記事中間
- 記事末尾
- サイドバー
- 固定フッター
などに「○○を無料で試す」「資料請求する」といった誘導ボタンを配置します。
3. ホワイトペーパー / 資料ダウンロード / 無料トライアルなどのCTAを増やす
ホワイトペーパー(専門ガイドや調査レポート等)を多数作成し、記事内で紹介することもリード獲得に有効です。ユーザーはホワイトペーパーのダウンロード時に問い合わせや会員登録をしてくれるため、コンタクトリストを拡充できます。オウンドメディアは単にアクセス数を増やすだけでなく、見込み客を育成し営業パイプラインに送客する役割も果たします。
リードの獲得方針はインサイドセールスとよく議論したうえで、運用できるような形でリード獲得していくとよいでしょう。
- リードはとれているものの、インサイドセールスのリソースがとれずに何も対策できていない
という状況になってしまうことを避けましょう。
SaaS SEO戦略の重要な要素
続いて、SaaS企業が効果的なSEO戦略を策定する上で押さえておきたい重要な要素を解説します。
ターゲットとなるユーザー像の明確化から、狙うキーワード選定の考え方まで、戦略立案のポイントを整理します。
1. ターゲットユーザー/企業の理解
まずは誰に向けて情報発信するのかを明確にする必要があります。
- どういう企業が対象なのか
- 担当者の役職はなんなのか
- 年間予算はどれくらいなのか
- どういう決裁フローなのか
- よく困っている課題はなんなのか
などについて、競合を踏まえて理解しておくことが重要になります。
ペルソナを設計する
自社サービスの典型的な顧客像(ペルソナ)を設計し、それぞれのペルソナが抱える課題や検索しそうな疑問を洗い出しましょう。たとえば、経理向けのSaaSなら「経理マネージャー」「中小企業の経営者」など複数のペルソナを設定し、それぞれが情報収集時に使うキーワードを想定します。
想像することが難しい場合は、実際にすでにクライアントとしている顧客を例にしてみるのがよいでしょう。
カスタマージャーニーを設計する
またカスタマージャーニー(購買までのユーザーの道筋)も考慮に入れます。
ユーザーが課題認識→情報収集→サービス比較→意思決定という段階を踏む中で、各段階で求める情報が異なるためです。たとえば認知・興味喚起フェーズでは「●●とは」「●●のメリット」といった一般的な疑問で検索し、比較検討フェーズでは「●● 他社比較」「●● 価格」といった具体的なキーワードになります。
キーワード戦略の策定
SEOの成否は、どのキーワードを選んで対策するかに大きく左右されます。ペルソナとカスタマージャーニーを踏まえ、ユーザーが各段階で入力しそうな検索語をリストアップしましょう。効率的に成果を出すため、次のポイントに留意してキーワード戦略を策定します。
すでにクライアントがいる場合は、過去の商談記録などを見た上で、「認知経路」や「課題感」などのログをみていると、思わぬキーワードが思いつくこともあります。
ユーザーの検索意図に応じてキーワードを分類する:
獲得するリードの種類がキーワードの熱量によって変わるため、キーワードを分類しましょう。
例として、
- 今すぐ購入意欲が高い商標系キーワード(例:「○○(自社サービス名) 料金」)
- 比較・検討フェーズ向けの比較系キーワード(例:「SaaS 比較」「○○ SaaS 評判」)
- まだそこまで比較熱量が高くない認知系のキーワード(例: SaaSとは)
などに分けます。上から順番に申込確度は高くなっていきます。
1に関しては、対策できていなければすぐに対策しましょう。工数が少なく、もっとも実現性が高く、インパクトが大きい施策となります。
2に関しては、多くの競合が狙っているキーワードのため、上位表示難易度が高く、初手で狙っていくのは少し難しいキーワードとなります。
3に関しては、すぐにリードは獲得できませんが、サービスの認知を獲得する上では重要なキーワードになります。
競合状況と自社ドメインの強さを分析する:
各候補キーワードについて検索結果を調査し、既に強力な競合サイトが上位を占めているかを確認します。
例を挙げると、例えば今から経理関連のSaaSを始める場合、競合にはFreeeやMoneyforwardがいます。
当然彼らは上場企業ですし、SEO対策もかなりリソースをさいているはずです。
そのため、いきなり「経理ソフト」でSEO対策しても上位表示される可能性は低いでしょう。
一方で、非常にニッチな市場に対して訴求したサービスを行っている場合、競合がいない可能性があり、継続的にコンバージョンが獲得できるケースがあります。
当社の自社開発しているアフィリエイト向けSaaSサービス「Media Analytics」は、同一カテゴリとなる競合がいないため、ユーザーが課題に感じることがあろう潜在的な認知系クエリ(月間Vol 1000程度)の記事を複数書いたところ、そこからリード獲得できたケースがありました。(具体的には、「リファラ 取得できない」という、市場の中で未解決の問題について、誰よりも熱量高く深く書いたコンテンツから認知を多く獲得できていました。)
もし競合が非常に強く、自社サイトのドメインパワーでは太刀打ちできない場合は、無理に正面から挑まずニッチな関連語で勝負する方が得策です。またSEOツールで自社サイトの権威性指標を把握し、比較的上位表示が狙いやすいキーワードを見極めます。
検索ボリュームと成果インパクトから優先順位を決める:
各キーワードの月間検索ボリュームや競合の弱さ強さを考慮し、投入リソースの配分を決定します。
一般に、ニッチだが確実にコンバージョンに繋がるキーワード(ボリューム小でも意図が明確なもの)と、将来的な集客源になり得るビッグキーワードの両方をバランス良く狙うのが望ましいです。
キーワードリストを作成して優先度をA/B/Cとランク分けし、順次コンテンツや対策を実行していきます。
ただし、ニッチなように見えて、参入している企業の予算規模が大きい企業の場合は、上位表示が難しいこともあります。
SaaSのSEO対策で申込(コンバージョン)を増やす仕組みとは
SEOの最終的な目的は流入増加だけでなくサービスの申込件数(コンバージョン)の増加です。
ここでは、SEO経由の訪問者を効果的に見込み顧客へと転換する仕組みづくりについて説明します。また、実際にSEO経由のコンバージョンが大きく伸びた事例も紹介します。
顧客との接点となるCTA(資料ダウンロード / ホワイトペーパー / 無料トライアル)を決めておく
まず最初に、どういう形でのリードがほしいのか確認します。
- 無料トライアル
- お問い合わせ
- 資料ダウンロード
- ホワイトペーパーダウンロード
先にこれらのリード種別を定義しておきましょう。
記事ごとに最適なコンバージョン動線を設計する
オウンドメディアの記事を公開する際は、各記事に適したコンバージョン動線(CTA)をあらかじめ決めておくことがポイントです。
記事の内容や想定読者の温度感に合ったCTAを設置することで、せっかく獲得したオーガニック流入をムダにせずリードへ繋げられます。
例えば、
- 初心者向けの入門記事であれば「●●の基本ガイドを無料ダウンロード」
- 比較検討系のキーワードなら「●●の無料トライアル」
といった、キーワードごとの熱量に応じて、CTAを出し分けていくことがおすすめです。
SaaSのSEO対策事例:CTAとコンテンツ改良による申込数増加
当社でご支援したクライアントのトライアル申込の件数が大幅に増加した事例があります。
CTAを見直し、ユーザーの興味を引く文言やデザインに変更しました。
同時に、新規に関連トピックの記事を複数追加し、既存の記事も最新情報を盛り込んでリライトしたところ、月間のサービス申込件数が以前と比べて大きく伸びました。

SaaSのSEO対策の成果指標
SEO施策を実行したら、その効果を定量的に測定・評価することが重要です。
SaaS企業における代表的なSEOの成果指標(KPI)として、サイトへの流入数、特定キーワードの検索順位、コンバージョン数の3つが挙げられます。それぞれの指標の見方と注意点を解説します。
流入数(セッション / ユーザー / ページビューなど)
まず基本となるのは、SEO経由でサイトに訪れたユーザー数です。これはGoogleアナリティクス4やGoogleサーチコンソールで計測できます。サーチコンソールでは検索クエリごとの表示回数やクリック数も把握できるため、どのキーワードからどれだけ流入しているかの分析に役立ちます。流入数は施策の初期段階で顕著に増えやすい指標なので、週次・月次でチェックしてコンテンツ公開やリライトの効果検証を行いましょう。ただし、一時的な流入増減に一喜一憂せず、季節変動やイベント要因も考慮して判断することが大切です。
対象キーワードの順位
流入の前提となるのが検索結果での上位表示です。狙ったキーワードで自社ページが何位にいるかを追跡することで、SEO施策の進捗状況を測れます。順位計測ツール(例:検索順位チェックツールのGRCやRank Trackerなど)を使えば、主要キーワードの順位推移を自動でモニタリング可能です。
コンバージョン数
最終的に最も重視すべきKPIがコンバージョン(問い合わせ件数や無料トライアル申込数など)の増加です。SEO経由のユーザーが実際にどれだけコンバージョンしたかを計測することで、施策の真のROIを評価できます。コンバージョンはGoogleアナリティクス4で目標イベントを設定するか、自社のCRMやSFAと連携して計測します。
SaaS企業がSEOを実施する際のベストプラクティス
最後に、SaaS企業がSEO施策を進める上で押さえておきたいベストプラクティス(成功のための実践知)を紹介します。限られたリソースや競合状況を踏まえ、無駄なく効果を出すためのポイントをまとめました。
すぐに成果が出るものではない
SEOは成果が出るまでに時間がかかる施策である点に注意が必要です。
コンテンツ公開直後からリードが劇的に増えることは稀で、多くの場合は数ヶ月~半年以上かけてじわじわ効果が現れます。
そのため初期のうちはコンバージョン数だけに囚われて判断せず、上述の流入数や順位など先行指標の伸びも合わせて観察しましょう。もし短期間で結果が出ないからといってすぐ施策を打ち切ってしまうと、せっかく育ちつつあるSEO効果が途絶えてしまう恐れがあります。
最低でも6ヶ月、できれば1年以上のスパンで改善を継続し、中長期でコンバージョン増につなげる視点が重要です。
また、記事を数記事入れただけでも、リードの数は劇的に増えません。まずはいったん作り切ることを意識して、行動をKPIにすると良いと思います。
競合と比較したときの自社のSEOの立ち位置を確認しておく
闇雲にSEOに投資を始める前に、まず競合他社のSEO状況と自社の現状ポジションを把握し、SEOに投資した時に勝算はあるのか確認しましょう。
もし競合がすでに多数のキーワードで上位を独占し、強力なオウンドメディアを展開している場合、後発の自社サイトが短期間で追いつくのは簡単ではありません。そのような場合でもSEO対策自体は重要ですが、投資に対する期待値と戦略を適切に設定する必要があります。
例えば短期的なリード獲得が必要だったり、そもそも事例を集めるところから始めなければならないフェーズでしたら、SEOよりもフォーム営業や広告運用、OrganicのSNSなどに予算を割いた方がよいでしょう。
一方で、検索市場においてニッチな隙間があるのであればキーワードやロングテールから攻める戦術を取るという方法も可能です。
ちなみにこちらの競合他社の状況は、SEOのコンサルタントではないと判断が難しいため、実績豊富なSEOコンサルタントに現状分析を依頼し、予算を投下すべきかどうか含めアドバイスをもらうのも有効です。(相見積もりを取る過程で、よい提案をしてもらえる可能性があります。)
大切なのは、競合との差を客観視した上で、自社にとって現実的かつ効果的なSEO目標を設定することです。
流入改善よりも先にコンバージョン改善
SEO施策に着手すると、どうしてもアクセス数(流入数)の増減に注目しがちです。しかし、真の目的は最終的な申し込みや契約数の増加にあります。したがって、コンバージョン率の低い状態でいくら流入だけ増やしてもビジネス成果には直結しません。例えば、サイトに訪れた100人中1人しか問い合わせしない状況では、仮に訪問者が2倍に増えても問い合わせは2件にしかなりません。そこでSEOに本格着手する前に、まずランディングページ(LP)や問い合わせフォーム、導入事例ページなどの改善を行いましょう。
外注するか内製するか → 先に内製して仕組みを整えておくと良い
SEO施策を自社で行うか、外部の専門業者に委託するかは悩ましいポイントです。両者はコスト面やノウハウ蓄積の面で一長一短があります。結論から言えば、初期段階ではできる範囲でいったんは社内メンバーで記事制作の流れを一通り理解したうえで内製し、自社なりの型やコンテンツ資産を築いておくことをおすすめします。
内製であれば社内にノウハウが溜まり、柔軟に施策を試行錯誤できます。具体的には、専任ではなくともマーケ担当者の中にSEOに明るいディレクター的な人材を1人配置し、小規模でもPDCAを回します。ある程度コンテンツ量が増え成果が出始めた段階で、外注の活用を検討すると良いでしょう。
例えば、記事制作の一部をSEOライターに委託したり、専門のSaaS向けSEO対策企業に運用を任せたりすることで、自社リソースを他業務に振り向けられます。外注する際も、内製経験があれば発注のポイントや評価基準が明確になるため、成果の出やすい発注運用が可能です。最初から丸投げするのではなく、まずは自社で仕組みを整え、その上で部分的にアウトソースするのが、長期的に見て効果と効率のバランスが取れた進め方です。
ホワイトペーパーを先に作るとSEOに効いてくる
前述のようにホワイトペーパー(お役立ち資料)はリード獲得に有効ですが、そのメリットはそれだけではありません。ホワイトペーパーを制作する過程で、関連する包括的なトピックを深掘りできるため、SEOで狙うべき具体的なキーワード群が明確になるという効果があります。
例えば「○○業界の最新動向」についてのホワイトペーパーを作成すれば、その中で触れたサブトピック(課題やソリューション)がそのままブログ記事のテーマになります。ホワイトペーパー自体もサイト上でPDFダウンロードページとして公開すれば、「○○ 業界 課題 ダウンロード」等の検索にヒットさせることができます。
さらに、一度作ったホワイトペーパーはコンテンツの原液となり、非常に品質の高いコンテンツとして再利用性が高い資産となります。
ホワイトペーパーを外注先に渡して、それを元にSEOの記事化を行うことで、外注先の業界知見が少なかったとしても高品質な記事を書くことが 可能です。
セミナー資料に転用することも可能です。加えて、ホワイトペーパーダウンロードというスムーズなコンバージョン動線を用意できるため、集客からリード獲得まで一貫した流れを構築しやすくなります。このように、まずはホワイトペーパーという包括的コンテンツを用意し、そこから派生する形で個別記事や施策を展開していくと、テーマの一貫性が保て、かつユーザーにも価値の高い情報提供ができるでしょう。
インサイドセールスと事前にマーケティングについて議論しておく
SEO施策によりホワイトペーパーのリードや問い合わせリストが増えても、その後のフォロー体制が無ければビジネス上の成果には結びつきません。特にB2B SaaSでは、営業前段階のリードに対し、インサイドセールス(内勤営業)やマーケティングオートメーションを活用したナーチャリングが不可欠です。そこで、SEOによるリード獲得施策を始める前に、自社のインサイドセールス(IS)チームやカスタマーサクセスチームとしっかり連携を取っておきましょう。
例えば、「ホワイトペーパーDLがあったら翌営業日中にISからフォローコールをする」「資料請求者向けに週1回の役立ちメールを配信する」「セミナーやウェビナーに誘導する」など、リードを顧客に育成する具体策をあらかじめ取り決めておきます。
この連携がないと、せっかく獲得した見込み客情報が宝の持ち腐れになってしまいがちです。SEO施策はサイト上で完結するものではなく、その後ろで営業・マーケティング施策全体が噛み合ってこそ最大の効果を発揮します。リード獲得から受注・顧客化までのフローを事前に社内ですり合わせた上でSEOを実施することが、成果を出すためのベストプラクティスです。
最後に:SaaS企業のSEO対策で重要なことは?
SaaS企業のSEO対策において必要なのは、
- そもそもSEOに対して投資を行ってどれくらいリターンが出るのか/そもそも投資すべきなのかを把握しておく
- SEOとインサイドセールス(もしくはカスタマーサポート)との運用方針を決めておく
- よいコンテンツを作るための運用体制についてしっかりと仕組み化しておく
といった点です。