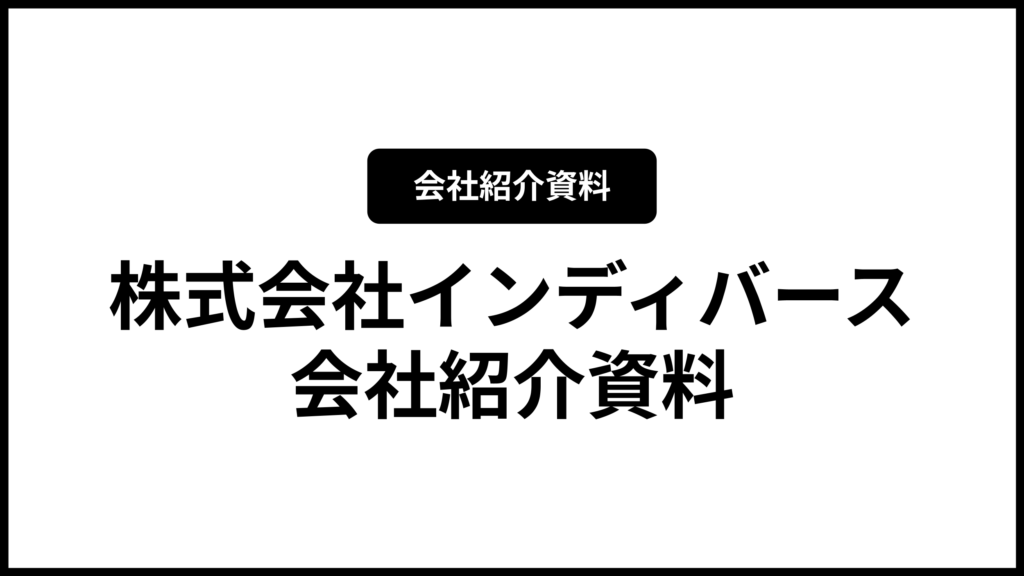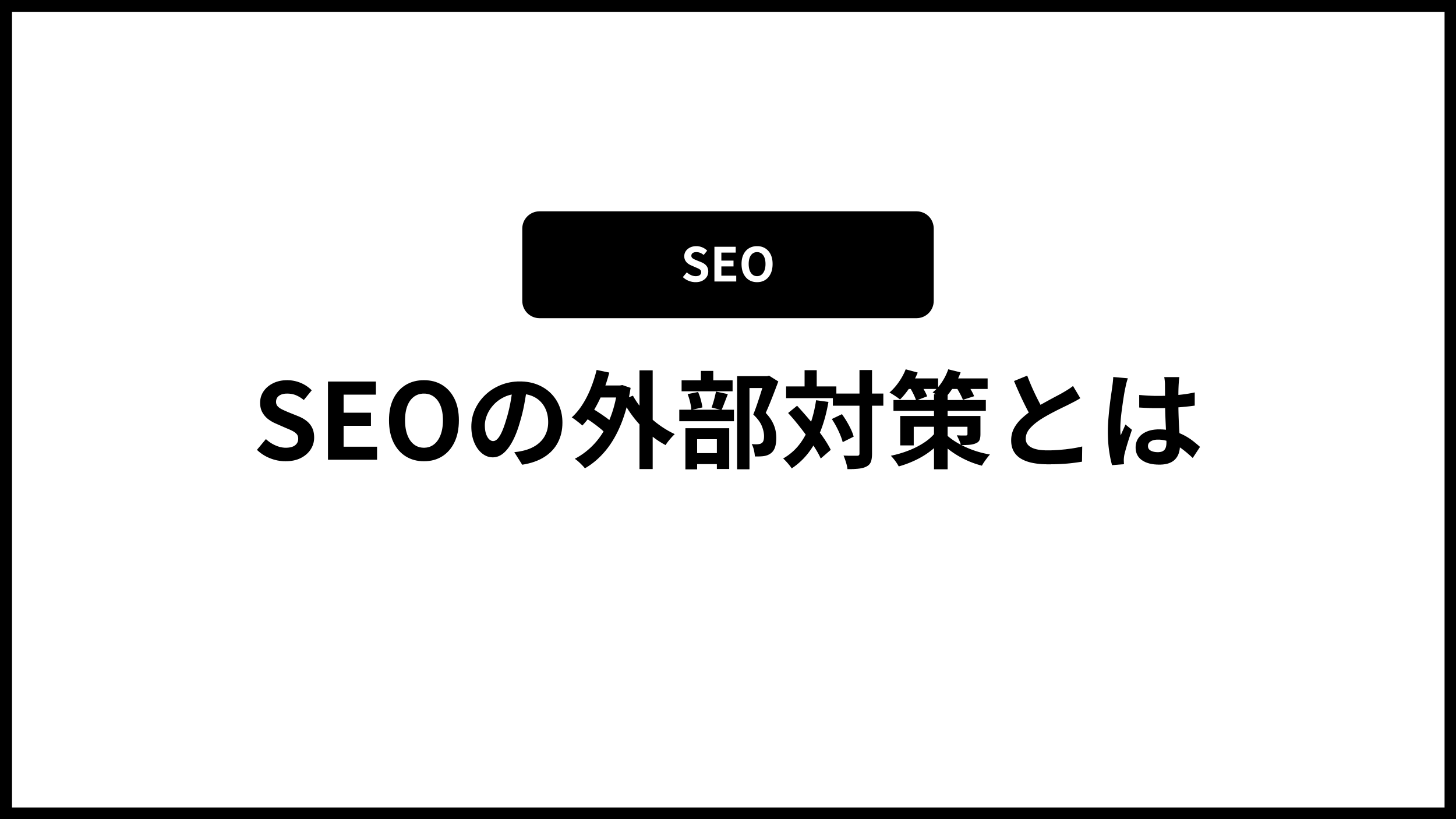
SEO外部対策とは、簡単に言えば自社サイト以外の外部要因を活用して検索エンジンでの評価を高める施策のことです。特に高品質な被リンク(他サイトから自サイトへのリンク)を獲得することが中心で、Googleはコンテンツと並んで被リンクを重要な評価基準としています
そのため外部対策は検索順位の向上やサイトの認知拡大に欠かせません。ただし、誤った方法でリンクを増やそうとするとGoogleからペナルティを受けるリスクもあるため注意が必要です。
また、外部対策は内部対策(サイト内の最適化)と両輪で進めることが重要で、どちらか片方だけでは十分な効果が得られない場合があります。
本記事では、当社が実際に外部対策を行いドメインランク(DR)を54まで高めた経験を踏まえ、
- SEOの外部対策の具体策(被リンク獲得方法)
- SEOの外部対策に関連するペナルティリスク
- 外部対策の費用感
について解説していきたいと思います。
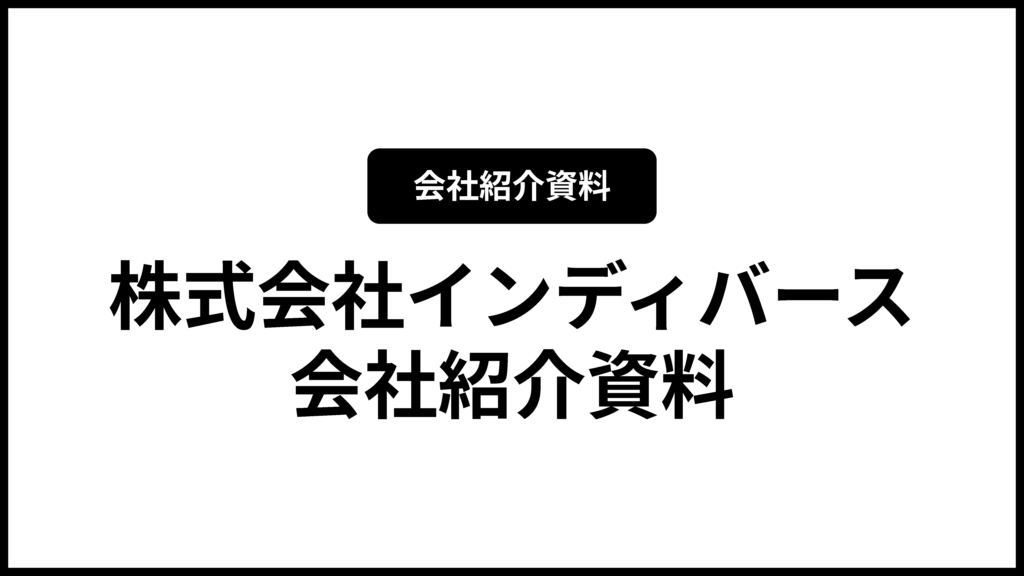
SEO施策全般にお困りの方へ
貴社のSEO施策全般の戦略立案から、実行までトータルサポート。
SEOコンサルティング/記事制作 / リライト/被リンク営業代行/Webアプリケーション開発 / 生成AI活用など、幅広く対応可能です。
SEO外部対策の定義と重要性
SEO外部対策とは、自社サイトの外で行うSEO施策全般を指します。
具体的には、他のウェブサイトから自社サイトへの被リンクを獲得したり、ソーシャルメディアでの言及や口コミを通じてサイトの評価を高めたりする取り組みです。
SEO対策は大きく「内部対策」と「外部対策」に分かれますが、内部対策がサイト内の改善であるのに対し、外部対策は外部サイトから被リンクを獲得する施策を意味します
なぜ外部対策が重要なのでしょうか。
その理由の一つは、Googleが検索順位を決定する主要な要因の一つに被リンク(外部からの評価)を挙げていることにあります。**が高いサイトほど検索順位が高いというデータもあります。
例えば、Brian Dean氏が1,180万の検索結果を分析したところ、サイト全体の被リンクの強さ(AhrefsのDRで計測)が高いサイトほど上位表示される傾向が確認されています。
このように、外部対策によって被リンクを増やしサイトの権威性を高めることは、SEO上非常に重要だといえます。
SEO外部対策と内部対策の違いを理解する
SEOにおける内部対策と外部対策の違いを明確に理解しておきましょう。
内部対策とは
内部対策は、自社サイト内で行う全ての施策を指します。
例えば、コンテンツの質を高めキーワードを適切に盛り込む、HTMLタグの最適化やサイト表示速度の改善、内部リンク構造の整理など、検索エンジンに正しく評価してもらうためのサイト内部の最適化が内部対策です。
外部対策とは
一方で外部対策は、前述の通りサイト外で行う施策で、主に他サイトから自サイトへのリンクを獲得することが中心となります。
内部対策が「オンページSEO(on-page SEO)」とも呼ばれるのに対し、外部対策は「オフページSEO(off-page SEO)」とも呼ばれます。
重要なのは、内部対策と外部対策は車の両輪であるという点です。
まずは内部対策で良質なコンテンツを揃えサイト自体の基礎体力をつけ、その上で外部対策によってサイトの権威性や信頼性を補強することが効果的です。
SEO外部対策が重要な理由
外部対策が重要視される理由はいくつかあります。ここでは主なポイントを整理します。
検索順位が上がりやすくなる
外部対策の最大の目的は検索エンジンでの評価向上です。他サイトからの高品質な被リンクは、Googleに「このサイトは信頼できる」というシグナルを送ります。被リンクが多いほどサイトのドメインランク(権威性指標)が上がり、結果としてSEO上有利になります。
実際、上位表示されているページほど被リンク数(特に異なるドメインからのリンク数)が多い傾向があり、被リンクはSEO成功に直結する重要要因なのです
露出増加によるブランド認知向上
外部対策を通じて他のウェブサイトに自社サイトが掲載される機会が増えると、ブランドの認知度が向上します。
業界のブログやニュースサイト、口コミサイトなどに自社サイトが紹介されリンクされることで、多くのユーザーの目に触れるようになります。
その結果、「○○というサービスを見たことがある」といった認知が広がり、指名検索(ブランド名での検索)をされる頻度が増える効果も期待できます。
指名検索が増えること自体、サイトの信頼性向上につながりうるため、間接的にSEO強化にも寄与します。
流入増加によるコンバージョン向上
他サイトからリンクされることは、SEO効果だけでなく直接的なトラフィック増加にもつながります。
例えば業界の人気サイトにリンクが掲載されれば、そのサイトの読者がリンク経由で自社サイトに訪れるでしょう。
こうしたリファラル流入は見込み顧客の誘導につながり、その分コンバージョン(問い合わせや購入など)の機会が増えます。
また検索経由の流入も、被リンク増加による順位向上で全体的に底上げされるため、結果的にサイト全体のアクセスと成果が向上します。
要するに、外部対策は検索アルゴリズム上の評価向上とユーザーへの露出拡大という二面の効果を持ち、サイトの集客力と信頼性を高める重要な施策なのです。
リンク獲得をする上で必要なdofollowの知識
外部対策で被リンク獲得を目指す際には、リンクに関する技術的なポイントも理解しておく必要があります。特に重要なのが「dofollow」と「nofollow」というリンク属性の違いです。
dofollow
dofollow(ドフォロー)とは、リンクが検索エンジンに対して評価を伝達する通常の状態のリンクを指します。
HTML上では特に特別な記述をしない限りリンクはdofollowであり、そのリンク先に PageRank(評価の投票)が渡されます。
言い換えれば、dofollowリンクはSEO的な価値をリンク先に送るリンクです。
nofollow
一方、nofollow(ノーフォロー)とはリンクにrel="nofollow"という属性を付与したもので、検索エンジンに「このリンク先には評価を渡さないでほしい」と伝えるものです。
nofollow属性が付いたリンクは、基本的にリンク先サイトのランキング向上には貢献しません(GoogleはnofollowリンクからのPageRankは 原則としてカウントしない としています)。
なぜこの知識が必要かというと、世の中に存在する多くのリンクが実はnofollowだからです。
例えば主要なSNS(TwitterやFacebookなど)に投稿したリンクや、多くのフォーラム、ブログのコメント欄のリンクは自動的にnofollowが付与されます。そのため、仮にSNSで大量にリンクがシェアされても、それ自体では直接的なSEO効果(リンクジュースによる評価向上)は得られません。また、Wikipediaなど信頼性の高いサイトの外部リンクもnofollowが付いています。
しかしながら、nofollowリンクにまったく意味がないわけではありません。
SNSでシェアされたりブログで言及されることは、それ自体がサイテーション(後述)となり得ますし、SNS経由で多くの人にコンテンツが届けば、その中から別のサイトで紹介してくれる人が現れる可能性もあります。
つまり、nofollowリンクは直接的にSEOパワーを渡さなくても、間接的な効果(認知拡大や二次的な被リンク獲得の契機)をもたらします。
サイテーションとは?
サイテーションとは、SEOにおいて「あるウェブサイトに関するリンク無しの引用・言及」のことを指します。
簡単に言えば、他のサイト上で自社サイトやブランド名がテキストで言及されることです(リンク付きで言及される場合は通常の被リンクとなります)。たとえば、「○○というサービスが便利らしい」とブログ記事内で紹介されたがリンクは貼られていない場合、その「○○」の部分がサイテーションに当たります。
サイテーションは特にローカルSEO(Googleマップ等での地域検索)の文脈で重要な概念です。
Googleビジネスプロフィールに登録した企業情報(名称、住所、電話番号など)が他サイトにも掲載・言及されているほど、そのビジネスの知名度が高いとみなされ、ローカル検索順位に好影響を与えると言われています。
しかし、サイテーションはローカルSEOに限らず一般的なSEO施策においても重要な要素です。他サイト上で自社について好意的に言及される回数が増えるほど、ウェブ上での評判が高まり、結果的にGoogleから信頼できるサイトと評価されやすくなります。
サイテーションと被リンク(dofollowリンク)の違いは、前者が評価伝達のない単なる言及であり、後者は評価を伝えるリンクである点です。
被リンクほど直接的にSEOスコアを押し上げる効果はないものの、サイテーションはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点でサイトの評判を支える重要な指標となります。
実際、Googleの検索品質評価ガイドラインでも、評価者に対して「サイトやコンテンツ制作者の評判を外部情報源から調査する」ことが求められています。
言及される回数や内容はそのサイトの第三者評価とも言えるため、良質なサイテーションを積み重ねることは結果的に検索エンジンからの信頼度向上につながります。
まとめると、サイテーションとはリンクの有無を問わない外部からの評価・言及であり、直接リンクパワーを伝えないもののサイトの評価に影響を与える要素です。
特にブランド構築の観点では重要ですので、被リンクだけでなく「正しく言及されること」にも目を向けて外部対策を行うと良いでしょう。
SEO外部対策の具体的な方法: アウトバウンド vs インバウンド
外部対策の具体的なアプローチには、大きく分けてアウトバウンド(能動的)とインバウンド(受動的)の2種類があります。
アウトバウンドなSEO外部対策とは?
まずは自ら積極的にリンクを獲得しにいく「アウトバウンド」の手法から見ていきましょう。アウトバウンド施策では、自社から働きかけて他サイトにリンクを張ってもらうよう依頼・調整します。
被リンク営業を行う
被リンク営業とは、他のウェブサイトに自社サイトのリンクを掲載してもらうよう直接依頼する取り組みです。
具体的には、関連業界のサイトやブログに連絡を取り、「当社の記事を紹介していただけませんか?」といった営業活動を行います。
単にお願いするだけでは相手側にメリットが薄いため、掲載してもらうためのインセンティブ(動機付け)を用意することが成功のカギです。
インセンティブの例としては、自社サービスの無償提供があります。
例えば自社で提供している有料ツールを相手サイトの運営者に無料で使ってもらい、その使用感を記事にしてもらう代わりにリンクを貼ってもらう、といった方法です。
また、寄稿(ゲスト投稿)も一般的な手法です。相手のブログに自社が役立つ記事を執筆し提供する代わりに、執筆者紹介や記事内で自社サイトへのリンクを入れさせてもらいます。
さらに、相互リンクも昔からある方法です。お互いのサイトにお互いのリンクを掲載し合う形で、双方にメリットをもたらすやり方です。ただし相互リンクは数が多すぎたり不自然だと評価が下がる恐れもあるため、関連性の高いサイト同士で節度を持って行うことが重要です。
注意すべき点は、金銭の授受によるリンク獲得は禁止されていることです。
お金を払ってリンクを買うこと(リンク業者に依頼する、ブロガーにお金を渡して書いてもらう等)は、Googleのウェブマスター向けガイドラインで明確にリンクプログラム違反とされています。「検索エンジンに影響を与える(PageRankを渡す)有料リンクはGoogleのガイドライン違反となります」というGoogle公式の発言もあるほどです。
そのため、被リンク営業のインセンティブはあくまで非金銭的な価値提供(無償サービス提供や情報提供など)に留め、金銭でリンクを買うブラックハットな手法は避けましょう。
アフィリエイト広告を行う
アフィリエイト広告を活用して被リンクを増やす方法もあります。これは、自社サービスや商品についてアフィリエイトプログラム(成果報酬型広告)を用意し、紹介してくれたパートナーに報酬を支払う仕組みです。具体的には、アフィリエイト用のリンク(トラッキングコード付きのURL)を発行し、ブロガーやサイト運営者がそのリンク経由でユーザーを送客してくれた場合に、成果に応じて紹介料を支払います。
アフィリエイトリンク自体は多くの場合nofollowもしくはrel="sponsored"属性が付与されます(Googleの推奨として、広告目的のリンクにはsponsored属性を付けることになっています)。
したがってリンクジュースという観点では直接的なSEO効果は期待できない場合が多いです。
しかし、アフィリエイトプログラムに参加したブロガーが自サイト上で積極的にあなたのサービスを紹介する記事を書くことで、結果的にウェブ上での露出が増えます。記事内でアフィリエイトリンクとは別にブランド名言及やレビューが掲載されれば、それ自体がサイテーションとなり評価にプラスです。
また、場合によってはアフィリエイトリンク以外に純粋な紹介リンク(dofollow)を貼ってくれるケースもあります。(例えば公式サイトのURLを直リンクなどで)
特にB2Cサービスや、一部の個人事業主向けB2Bサービスではアフィリエイトは有効です。
例えば通販系サイトやサブスクリプションサービスなどは、多くのアフィリエイトブロガーが比較記事や体験談を書いてくれるため、一気に多数のサイトから言及・リンクされる可能性があります。
ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)と呼ばれる仲介サービス(例えばA8.netやもしもアフィリエイトなど)に自社プログラムを載せれば、興味を持った提携希望者を募ることができます。
アフィリエイトは成果報酬なので初期費用を抑えつつ外部露出を増やせる手段ですが、提携するブロガーの質(記事内容)によってはブランドイメージに関わるため、プログラム条件や参加者の管理も適切に行う必要があります。
有料媒体掲載を行う
有料媒体への掲載とは、費用を支払って特定のウェブ媒体に自社情報を掲載してもらうことです。
一種のPR的なアプローチですが、狙いとしては高品質なバックリンクの獲得にあります。ビジネスマッチングサイト、業界の企業名鑑サイト、製品レビューサイトなど、有料プランで自社ページを持てる媒体がこれに該当します。
例えば、B2B企業向けのサービス比較サイトやポータルサイトでは、有料会員になることで自社サービス紹介ページを作成し、その中に公式サイトへのリンクを載せられるものがあります。
また、プレスリリース配信サービス(PR TIMESなど)は有料ですが、配信したリリース記事内に自社サイトリンクを入れることで、Yahooニュースや各種ニュースサイトに転載された際にリンク付きで掲載されるケースもあります。
さらに採用媒体(求人サイト)の企業ページに自社ホームページのリンクが掲載できることも多く、採用目的で媒体掲載することで結果的に被リンクを得ることもできます。
日本市場においては、例えば「○○業界ポータルサイト」や「○○比較サイト」といった媒体がいくつも存在します。こうした媒体はドメインパワーが高いことが多く、そこからのリンクは質が高いと考えられます。
ただし掲載には月額費用や初期費用が発生することもあるため、費用対効果を検討しましょう。アクセス流入や営業上のメリットも得られる媒体であれば、一石二鳥です。また、有料掲載媒体を利用する際も、リンク属性(nofollowになっていないか)を確認することをおすすめします。
媒体によっては広告案件扱いでnofollowになる場合もあるためです。
いずれにせよ、お金を払ってでも掲載する価値ある媒体に露出することは、被リンク獲得とブランド認知の両面でメリットがあります。ただし、前述のように単なる「リンク購入」にならないよう、あくまで媒体掲載という正規の形で行うことが重要です。
SEO外部対策の具体的な方法:インバウンド
次に、インバウンド(受動的)な外部対策、つまりこちらから働きかけなくても自サイトに自然とリンクが集まる仕組みを作る方法を解説します。インバウンド施策では、主に自社の情報発信やプロダクト作りによって結果的にリンクを引き寄せます。
これが個人的には王道だと思っています。
プレスリリースや広報活動を活用する
自社のニュースや成果をプレスリリースとして発信することは、外部対策として有効です。
プレスリリースを配信すると、それを元に複数のメディアが記事を書いたりニュースサイトに転載されたりします。
例えば、新サービスのローンチや大きな資金調達の発表をPR TIMESなどで配信すると、Yahoo!ニュースや業界メディアにリリース情報が掲載され、自社サイトへのリンクが貼られることがあります。
また、広報担当者がいる場合は、積極的にメディアに売り込みをかけて取材記事を書いてもらう努力も大切です。
メディア掲載の記事内には高頻度でサービス紹介のためのリンクが掲載されます。
プレスリリース自体のSEO効果については賛否ありますが、少なくとも知名度向上と信頼性の醸成には大いに役立ちます。
信頼度の高いニュースサイトからリンクが張られるのは、検索エンジンにとっても大きなプラス評価です。また、一度報道されると他のサイトやブログがそれを引用して記事を書くこともあり、二次拡散でさらなる被リンクを得られる可能性もあります。
ポイントは、本当に話題性のある内容をタイミングよく発信することです。「PR」のためだけに内容の薄いリリースを乱発しても効果は薄いため、広報戦略の一環として質の高い情報を発信しましょう。
誰もが参照したくなるような質の高いコンテンツを作成する
「コンテンツSEO」という言葉があるように、良質なコンテンツ作りは内部対策として語られがちですが、実は外部からリンクを引き寄せる土台にもなります。他にはないオリジナル性の高い情報や、有益でまとまった記事は、多くの人が参考にしたり他サイトで「このページが参考になる」とリンクを貼ってくれたりします。言い換えれば、サイト内にリンクを張りたくなるようなコンテンツを用意することが、自然な被リンク獲得への近道です。
具体例としては、業界の統計データや調査結果をまとめたページ、専門知識を分かりやすく解説したホワイトペーパー、あるいは他では得られない一次情報を含む記事などが挙げられます。たとえば、「○○市場の最新動向2023年版(独自アンケート結果付き)」のような記事を作成すれば、他のブログがそのデータを引用する際にあなたのサイトを出典リンクとして紹介するかもしれません。また、「業界トップ10社のサービス機能を徹底比較」といった読み応えのある調査記事は、後発の似た記事を書く人にとって参考資料となり、リンクが貼られることがあります。要は、自社サイトを情報源として利用してもらえる状態を作るのです。
現に、例えば、この記事では
例えば、Brian Dean氏が1,180万の検索結果を分析したところ、サイト全体の被リンクの強さ(AhrefsのDRで計測)が高いサイトほど上位表示される傾向が確認されています。
という引用を行っています。
これは「外部対策って有用だよね」という根拠を探したいときに必ず参照したくなるような調査だからなんですよね。
質の高いコンテンツを作ることは一朝一夕にはいきませんが、それ自体が半永久的な資産となり、継続的にリンクを生み出す可能性を秘めています。SNSでバズるような面白ネタ記事も瞬間的なリンク獲得にはつながりますが、SEO観点では恒常的に引用される定番コンテンツを持っておく方が強力です。コンテンツ制作は内部対策と考えがちですが、その成果が外部評価(リンク)を呼び込むことを意識して、戦略的にネタを選定しましょう。
プロダクト自体にリンクが獲得できる仕組みを入れる
外部対策の中級〜上級テクニックとして、自社のサービス・プロダクトそのものにリンクを生み出す仕掛けを組み込む方法があります。
たとえば、自社提供のツールやウィジェットを他サイトに埋め込めるように提供し、埋め込みコード内にさりげなく自社サイトへのリンクを含める、といった施策です。
具体例を挙げると、Webサイト向けの小さなウィジェット(例えば為替レート表示ツールや天気予報パーツなど)を開発し、自由に使えるコードを配布します。そのコードに「提供:○○(自社名)」という形で自社サイトへのリンクを含めておけば、埋め込んだ多数のサイトからリンクが集まります。
同様に、バッジ(利用中であることを示す画像とリンク)を発行するのも有効です。これは「当社のサービスを利用中である証」をサイトに貼ってもらうもので、「○○ Certified」といったバッジ画像をユーザーが自分のサイトに貼り付け、その画像に自社へのリンクを設定してもらう仕組みです。
ユーザーに価値を提供しつつリンクも得られるため効果的です。
ほかにも、プラグインやアプリを公開することで公式ストアからリンクを得る方法もあります。例えばiOSアプリを公開すればAppleの公式App Store内に開発元サイトへのリンクが掲載されますし、WordPressやShopify向けのプラグインを開発して公開すると、それらのディレクトリサイトからリンクが張られます。(nofollowですが)
こうした大手プラットフォームからのリンクは非常にドメインパワーが強く、SEO上も価値が高いと考えられます。
さらに、サービス系サイトの場合はユーザープロフィールページを戦略的に作るのも手です。ユーザーが自分のプロフィールや実績ページを持てるSNS・プラットフォームでは、ユーザー自身がそのページURLを他所で共有・紹介してくれることがあります(例:○○さんのページはこちら→自社ドメイン)。結果として自社ドメイン配下のページへのリンクがインターネット上に増えるわけです。
Web制作会社なら、「価格は安くするのでフッターにPowered by インディバース」というリンクを入れられないか?」と交渉して、クライアントから被リンクを獲得するという方法もあります。
これらの手法はいずれも「競合他社が簡単には真似できないリンク獲得」を実現するものです。
プロダクトやサービスの設計段階から「リンクを生む仕組み」を組み込めれば、継続的かつ半自動的に被リンクが増えていく強固な外部対策となるでしょう。
SNSを通じた情報発信
SNS(ソーシャルメディア)での情報発信も、外部対策と併せてぜひ行いたい施策です。前述したようにSNS上のリンクは基本nofollowですが、SNS活用には別のメリットがあります。それは、コンテンツの拡散と認知度向上です。
例えば新しく公開した記事や資料をTwitterやFacebook、LinkedInなどで積極的にシェアすると、多くのユーザーの目に触れることになります。直接リンクジュースは得られなくても、内容が優れていればいいねやリツイートによって一気に話題が広まり、結果としてそのコンテンツをネタにブログ記事を書く人が現れたり、ニュースメディアに取り上げられたりする可能性が高まります。
実際、当社でもオウンドメディアの記事をTwitterで発信したところ業界インフルエンサーに見つかり、それがきっかけでいくつかの媒体に紹介されリンクを獲得できた事例があります。SNSは言わば外部対策の起爆剤として機能するのです。
また、SNS経由でサイトのブランド認知が上がると、指名検索の増加やコミュニティでの評判醸成にもつながります。
これらは直接的なSEO要因ではないものの、総合的なサイト評価に良い影響を与えます。特に新興サイトの場合、最初はどんなに良い記事を書いてもドメインパワーが低ければ検索上で埋もれてしまいます。
しかしSNSを活用すれば、ドメインランクが低いうちからでも人の目に触れる機会を作り出せるため、被リンク獲得のスピードを早める効果があります。
要するに、SNS単体ではSEO効果は限定的でも、SEOと組み合わせることで相乗効果を生みます。外部対策を本格化する際は、ぜひSNS運用も並行して行い、コンテンツの露出とリンク獲得チャンスの最大化を図ってください。
SEO外部対策におけるペナルティ
外部対策を進める上で気を付けなければならないのが、Googleからのペナルティです。外部施策で成果を急ぐあまり、ガイドラインに違反するような手段を取ってしまうと、かえって検索順位を大きく落とすリスクがあります。以下、主要なペナルティ要因をまとめます。
有料リンクの購入は禁止 –
繰り返しになりますが、金銭でリンクを買う行為は厳禁です。Googleはリンク販売・購入などランキング操作を目的としたリンクスキーム全般をペナルティの対象としています。実際に過去には大規模なリンク売買ネットワークが摘発され、関与したサイト群が軒並み圏外に飛ばされるという事例も起きています。Google公式ブログでも「検索エンジンに影響を与える有料リンクはガイドライン違反」と明言されています
低品質なリンクの大量獲得は危険
質の低い被リンクが大量にある場合、Googleからスパムと見なされペナルティを受ける可能性があります。
低品質なリンクとは例えば、
- スパムサイトやサテライトサイトからのリンク
- 意味の薄いサイト同士で貼り合った過剰な相互リンク
- リンクプログラムによる大量のリンク一括購入
- 過去に権威性が高かったサイトの中古ドメインから貼られたリンク
などです。
これらはいずれも「検索順位を人為的に操作しようとする不自然なリンク」と判断されます。
Googleはリンクの質も重視しており、権威ある関連サイトからのリンクは評価しますが、そうでないリンクが多数あると逆効果です。
万一、自社サイトにこうした低品質リンクが多数貼られている場合は、Search Consoleのリンクレポートを確認し、不自然なリンクは否認ツールを使ってGoogleに無効化申請することも検討しましょう。
ワードサラダ等のスパム行為
一昔前に流行った手法ですが、無意味なキーワードを羅列しただけの「ワードサラダ」記事を量産し、そこにリンクを埋め込んでばら撒くような行為も避けるべきです。
現在ではこの種のコンテンツは検索エンジンにほぼ相手にされず、実質的に無効化されています。Googleは価値のない自動生成コンテンツをスパムポリシー違反として扱っています。
外部対策では「質の低いページからのリンクはいくら増やしても意味がない」ことを念頭に置き、健全な方法に注力することが大切です。
ペナルティを受けたサイトからのリンク
これは自分では制御しづらい部分ですが、リンク元のサイト自体がGoogleからペナルティを受けている場合、そのリンクも評価されないか、最悪マイナスの影響を及ぼす可能性があります。
一般的に、Googleが手動ペナルティを科すようなスパムサイトからのリンクは無視される傾向がありますが、大量だと負のSEO(ネガティブSEO)的に作用するリスクも否定できません。自サイトに覚えのない低品質サイトからのリンクが増えている場合は注意し、必要ならリンク否認も活用してください。
SEO外部対策の効果測定とツール
外部対策の成果を把握し、改善に活かすためには効果測定が欠かせません。以下のようなツールを活用して、自社の被リンク状況や競合との差をチェックしましょう。
Googleサーチコンソール(Google Search Console)
Googleが無料提供している公式ツールです。サーチコンソールの「リンク」レポートでは、自社サイトに対して「どのサイトから何件リンクされているか」や「よくリンクされているページ」「アンカーテキスト」などを確認できます。
特に外部対策では、定期的にこのレポートを見て被リンク数の推移を追いましょう。新たに獲得できたリンクや、逆に消えてしまったリンクを把握できます。また、サーチコンソールは手動ペナルティの通知も受け取れるので、外部リンクに起因するペナルティ発生時の早期発見にも役立ちます。導入はサイト所有者であれば必須と言えるでしょう。
Ahrefs(エイチレフス)やSemrush(セムラッシュ)
代表的な有料SEO分析ツールです。これらのツールでは自社・他社含めたサイトの詳しい被リンクプロファイルを調査できます。
特にAhrefsは被リンク解析が強みで、独自のクローラによる膨大なリンクデータベースを持っています。Ahrefs上ではドメインレーティング(DR)や被リンク数、参照ドメイン数などが一目で分かり、リンク元サイトの質まで分析可能です。
Semrushも類似の機能を持ち、加えて競合比較に優れています。例えば競合サイトと自社サイトの被リンク数やスコアを比較したり、競合だけが持っていて自社にないリンク(ギャップ分析)を洗い出したりできます。
これにより「競合A社は○○というサイトからリンクを獲得している」など具体的な情報が得られ、競合の外部対策戦略を推察することも可能です。
MozやMajesticなどその他ツール
Mozが提供するDomain Authority(DA)もドメイン評価指標として知られていますし、MajesticのTrust Flow/Citation Flowもリンクの質と量を測る指標です。各社で算出方法は異なりますが、傾向を掴むうえでは参考になります。複数の指標を併用して、自社サイトの権威性が上がっているかどうかをモニタリングすると良いでしょう。
外部対策を行った上で注意点:実際にDR54まで上げた上での経験談
ここでは、当社がゼロから新規ドメインで外部対策を行ってドメインランク(Ahrefs DR)を54まで高める中で痛感した、「事前に知っておきたかったポイント」や注意点を共有します。同じように外部対策に取り組む方にとって有益なヒントとなるでしょう。
被リンク営業はインセンティブ作りが必要
外部対策の初期段階で、多くのサイトが直面するのが「被リンク営業してもなかなか相手にされない」問題です。特に自社サイトの知名度やドメインランクが低い状態だと、お願いしても掲載メリットを感じてもらえず、断られるケースが大半でした。この経験から学んだのは、相手にとって魅力的なインセンティブを用意することの重要性です。
例えば当社では、ある程度自社サイトのDRが上がってきた段階で、関連業界のサイトに相互リンクや記事交換を持ちかけました。しかし、DRが10台だった頃は返信率が低く、話が進みませんでした。相手にとって当社サイトからのリンクの価値が低かったからです。そこでまず先に内部施策やSNSでDRを20以上に上げ、自サイトの評価を高めてから再アプローチしたところ、応じてもらえる確率が上がりました。「DR20以上ならリンクする価値がある」と判断してもらえたのです。同様に、寄稿提案をする際も自社にそれなりのトラフィックや評価がないと割に合わないと思われてしまいます。
教訓としては、自社サイトの価値をある程度高めてから被リンク営業をするのが得策ということです。最低でもDRが20くらいあると、「こちらからもそちらにリンクできます(互恵性)」という提案がしやすくなります。また、相手に響く提案文も工夫しましょう。ただ単に「リンクしてください」ではなく、「御サイトの記事○○で紹介されているテーマに関連する当社の記事△△をぜひご参考にリンクいただけますと〜」といった具体的メリットや根拠を示すと、相手の納得感が違います。
被リンク営業を行う前に、コンテンツは100記事最低入れておくと良い
上記と関連しますが、被リンクを依頼する前提として自サイトにコンテンツが十分あることが重要です。当社の経験では、サイト内の記事数がごくわずかな頃にリンク依頼をしても、「貴社サイトを拝見しましたが、まだ記事が少ないようなので…」と断られたり、相手にされなかったりしました。
相互リンクや寄稿の話を持ちかける場合、相手サイトにとってもリンクする価値のあるページが必要です。自社に全く記事がなければ、相手はリンクを貼る先がないか、載せる意味がないと判断してしまいます。そこで、外部対策の本格着手前にまず100記事程度のコンテンツ蓄積を目指すことをおすすめします。100という数字は一つの目安ですが、それくらい記事があれば自社サイトのテーマや強みも見えてきますし、中には検索上位に食い込んでいる記事も出てくるでしょう。そうした「このジャンルなら御サイトの記事を引用したい」と思ってもらえるネタがある状態だと、リンク提案の成功率が格段に上がります。
当社では先にオウンドメディアの記事を100本以上投入し、その中で専門性の高い記事やバズった記事をいくつか作り出すことに注力しました。その上で「〇〇に関する情報なら弊社の記事△△が参考になりますのでリンクしませんか?」といった具体的なページ単位での依頼を行うようにしたところ、前向きな返答が増えました。「確かにこの情報は自サイトのユーザーにも有益だからリンクしてもいい」というフェーズに持っていくのが大切です。
被リンク営業において、フォームの文面・訴求で、返信率が2倍くらい変わる
被リンク営業の方法として、相手サイトのお問い合わせフォームから依頼メッセージを送る「フォーム営業」を行うケースがあります。その際に痛感したのが、送る文面の工夫次第で返信率が大きく変わるということです。
当社では多数のサイトにフォーム営業を行いましたが、初期のテンプレート的な文面では返信率が低迷しました。そこで、相手サイトごとにカスタマイズした内容(相手の記事内容に具体的に触れ、その補足になる当社記事を提示する等)を書き込むようにしたところ、返信率が明らかに向上しました。また、自社サイトのDRが向上するにつれて返信率も上がりました。実データで言えば、DRが50を超えた頃にはフォーム営業経由の返信率が約9〜12%に達し、DR20前後の頃の5%未満から倍増したのです。これは、「相手が当社からのリンクに価値を感じてくれるようになった」ことと、「メッセージ内で提示する当社メリットが明確になった」ことの両面が要因でした。
教訓として、フォーム営業では相手目線でのメリット訴求を入れること、そして自社サイトの指標(DRなど)が高くなってから行うことが効果的です。更に、件名の付け方や文章の丁寧さなども信頼性に影響します。雑な一斉送信のような依頼は読まずに破棄されがちなので、できる限り一通一通パーソナルなメッセージを心掛けましょう。
外部対策が全てではない
外部対策を進めていると、ついドメインランク(DRやDA)など数値目標ばかりに目が行きがちです。
しかし実際の検索結果を見ていると、DRがわずか2程度の新興サイトが、DR50の競合サイトより上位に表示されているケースもありました。つまり、ドメインの強さがすべてを決めるわけではないのです。
その理由として考えられるのは、被リンクの質や他の要因です。
低DRでも、極めて権威あるサイト(大学や行政など)から少数の良質なリンクを得ているサイトは、量だけ多いリンク群を持つサイトより評価が高い可能性があります。また、SEOの評価軸はリンクだけではなく、コンテンツの関連性・網羅性、ユーザーエンゲージメント(直帰率や滞在時間など)、さらにはSNSでの人気や指名検索の量といった様々なシグナルがあります。総合的に見て優れているページであれば、ドメインパワーが弱くとも上位に来ることは十分起こります。
我々も最終的にDR50台まで向上させましたが、その途中でDRばかり追いかけてコンテンツ更新が疎かになった時期は、思うように順位が伸びませんでした。
SEOはレーダーチャートのようなものだと感じます。外部対策(被リンク)はその一角を担う重要要素ですが、それだけ尖らせても他がゼロでは上位表示は難しいのです。
ですから、「ドメインランク=SEO力」と短絡的に考えず、コンテンツ品質やユーザー体験の向上にも並行して注力しましょう。ドメインの強さは重要な武器ではあるが万能ではない――この認識を持つことが健全なSEO戦略と言えます。
SNSはSEOと一緒に絶対にやっておいた方が良い
SEOのみで外部対策を行う時、最初の壁は
- ドメインが弱いので、相互リンクの営業ができない
- 記事が上位表示されていないので、相互リンクの影響ができない
- 記事が上位表示されていないので、そもそも引用されない
という問題が起こります。なので、自然にリンクされるのに非常に時間がかかります。
一方で、実際に我々はSEOとSNSを並走させたことで大きな恩恵を受けました。
特にサイト立ち上げ当初、SNSでの発信だけで、DRを20近くまで押し上げることができ、非常にスムーズに被リンク獲得の初動を切れたと実感しています。
SNSを活用する最大の利点は、良いコンテンツを早期に広められることです。
検索流入だけに頼っていると、ドメインランクが低いうちはせっかくの良記事もなかなか人に読まれず、リンクされる機会も訪れません。しかしX等で直接記事をターゲットユーザーに届ければ、興味を持った人が即座に反応し、それが拡散され・・・という形でリンク獲得のきっかけが何倍にも増えます。
実際当社でも、SNSでバズった記事がいくつかあり、その結果業界の有識者ブログから引用リンクをもらえたり、大手ニュースサイトに取り上げられたりしました。
また、SNS上でファンやフォロワーが増えると、ブランド力が高まり指名検索も増える傾向にあります。
これは直接SEOランク要因ではないにせよ、サイト全体の評価にはプラスです。
何より、SNSとSEOは相互補完的です。SNS経由で被リンクが増えればSEO効果でさらに露出が増え、SEOで知ったユーザーがSNSでフォローして拡散してくれる・・・という好循環が生まれます。どちらか一方だけでは得られない相乗効果があるので、SEO担当者こそSNSも積極的に活用すべきでしょう。
競合が獲得しづらいリンクを仕組みとしてずっと取れると強い
最後に、外部対策を長期的な視点で考えたときのポイントです。
それは、競合他社が簡単には真似できないようなリンク獲得源を持つことの強さです。
例えば、当社のクライアントですが、大学機関へのインタビューを行い、その結果を大学の公式サイトで紹介してもらっています。
大学のサイト(ac.jpドメイン)からのリンクはDRこそそれほど高くない場合もありますが、非常に高品質でテーマ関連性も高いリンクでした。
大学機関からの被リンクは、とにかく最初の数本の実績獲得が大きな参入障壁になります。最初の実績さえあれば、他の大学もインタビューに答えてくれますからね。逆に最初の一本の獲得が難しい。
また、自社がサービスサイト(プロダクト提供)である強みがあるクライアントも強いでしょう。
送客メディアではなく、自社でサービスを持っているような企業であれば、リンクを獲得しやすいです。
先述の通り、サービス系サイトは例えば「おすすめ○選」記事に掲載されやすい傾向があります。
特に、市場では大きく需要があるのに、供給が少ないエッジが効いたサービスであればあるほど、ピンポイントでおすすめ記事に載りやすいです。
メディアサイト(コンテンツのみのサイト)は他メディアからリンクされる機会は少ないですが、サービスならレビューサイトや比較記事からリンクをもらいやすいのです。競合他社が媒体を持っていないような場にも当社サービスを乗せ込むことで、唯一無二のリンクソースを増やせます。
重要なのは、単発の思いつきではなく仕組みとしてリンクを取り続ける体制を作ることです。
体制は、プロダクトそれ自体かもしれませんし、対象とする市場環境かもしれません。とにかく、紹介されやすい文脈づくりが重要になります。
SEO外部対策に関するよくある疑問
最後に、SEO外部対策について多くの方が抱きがちな疑問をピックアップし、Q&A形式でお答えします。
外部対策はいつからやるべきか。
回答:
サイトの状況によって異なりますが、ベーシックなリンク営業をメインで実行する場合は、基本的にはまず内部コンテンツをある程度充実させてから外部対策に取りかかるのが望ましいです。
具体的には、オウンドメディア記事がいくつか(理想的には数十記事以上)揃ってからが目安です。
理由は、上位表示されているコンテンツがない状態で被リンク営業などを行っても、リンクしてもらうための材料もインセンティブも相手になく、成果が出にくいからです。
まずは内部対策とコンテンツ制作に注力し、上位表示される記事を先に作りましょう。
その上で、公開済みの記事を他サイトに紹介したり、プレスリリースで発信したりといった外部対策を順次始めると効果的です。
ただし、SNSアカウントの開設や自社紹介のポータルサイト登録など、すぐにできる外部施策はサイト立ち上げ時から行っておいて損はありません。
内部施策と外部施策のバランスを見ながら、タイミングをずらして段階的に外部対策を強化していくと良いでしょう。
外部対策の費用はどれくらいですか?
回答:
外部対策にかける費用は、施策内容や担当者リソースによって大きく異なります。
自社内で工夫して進める場合は、基本的に人的コスト(時間や労力)が中心になります。
一方、外部のSEO業者やコンサルに依頼する場合は月額10〜20万円前後の費用が発生するケースが一般的です。
例えば被リンク獲得代行サービスでは、毎月決められた数のサイトにフォーム送信・交渉をしてくれるプランがそのくらいの価格帯で提供されています。
ただ、交渉次第で費用は上下し、一件ごとの成果報酬型を採用している業者もあります(ただしこうした業者選定は慎重に、ガイドライン遵守の会社か確認必須です)。
自社で行う場合でも、寄稿記事を書く工数や人件費、プレスリリース配信費用(1本数万円程度)など間接的な費用はかかります。
結果を出すために必要な投資と考え、予算内で最大限効果の出せる施策を選びましょう。
なお、闇雲にお金をかければ良いというものではなく、低品質なリンク購入に費用をかけるのは逆効果なので注意してください。
SEO外部対策の効果が落ちているというのは本当ですか?
回答:
一部で「最近は外部(被リンク)の効果が以前より薄れている」という声を聞くことがありますが、必ずしも外部対策が無意味になったわけではありません。
Googleのアルゴリズム更新の度に、コンテンツの重要度が増したり、逆にリンク評価がメインに戻ったりという変動は確かにあります。
例えば近年はE-E-A-Tなどコンテンツの信頼性を重視する傾向もあり、リンク偏重だった昔と比べれば評価のバランスは変わっています。(2025年8月現在)
しかし、Google自体が「コンテンツとリンクはランキングの主要因」と表明しているように、高品質な被リンクの価値は今も健在です。
ただし低品質なリンクでのごまかしが効きにくくなったため、「外部対策=リンク集めればOK」という短絡的手法は通用しづらくなっています。
総じて、外部対策の効果がゼロになったわけではなく、質と手法の洗練が求められていると考えるべきでしょう。
アップデートの度に多少の波はありますが、長期的には良いコンテンツに良いリンクが集まる構図は変わらないはずです。
ですので、外部対策が衰退したと捉えるより「手法が進化している」と捉え、正攻法での取り組みを続けることが大切です。
外部SEOとは何ですか?
外部SEO(外部対策)とは、自社サイト外で行うSEO施策の総称です。主に他サイトから自社サイトへの被リンクを獲得したり、SNSや第三者サイト上でブランドやサイトが言及されるよう働きかけたりする取り組みを指します。簡単に言えば「外部から自サイトの評価を高めるための施策」です。
SEOの外部対策と内部対策の違いは何ですか?
外部対策は自サイト外での施策(被リンク獲得やサイテーションなど)、内部対策は自サイト内での施策(コンテンツ最適化やサイト構造改善など)です。内部対策はサイトそのものを良くする作業、外部対策は他者からサイトを推薦・評価してもらうための作業、と覚えると分かりやすいでしょう。