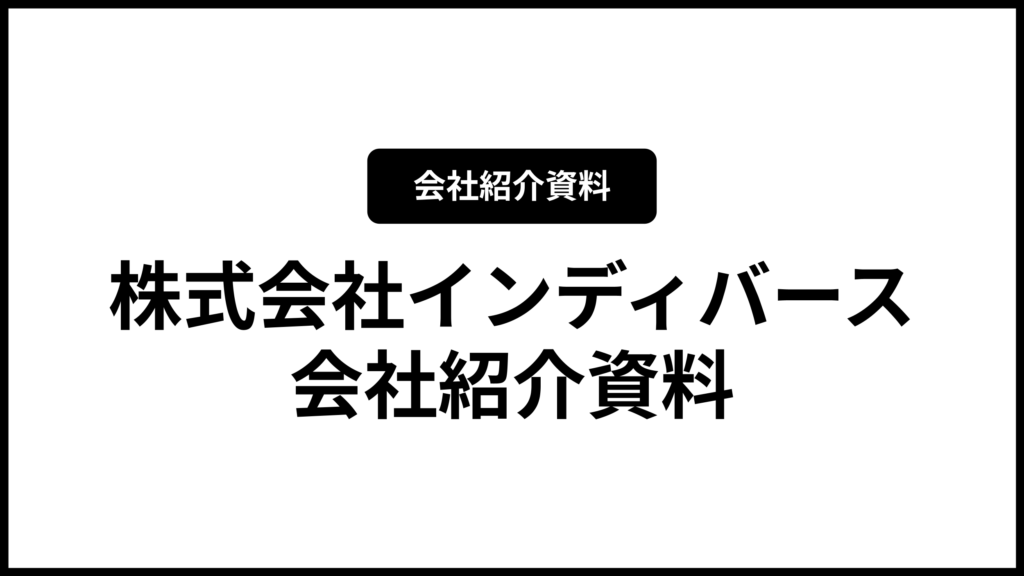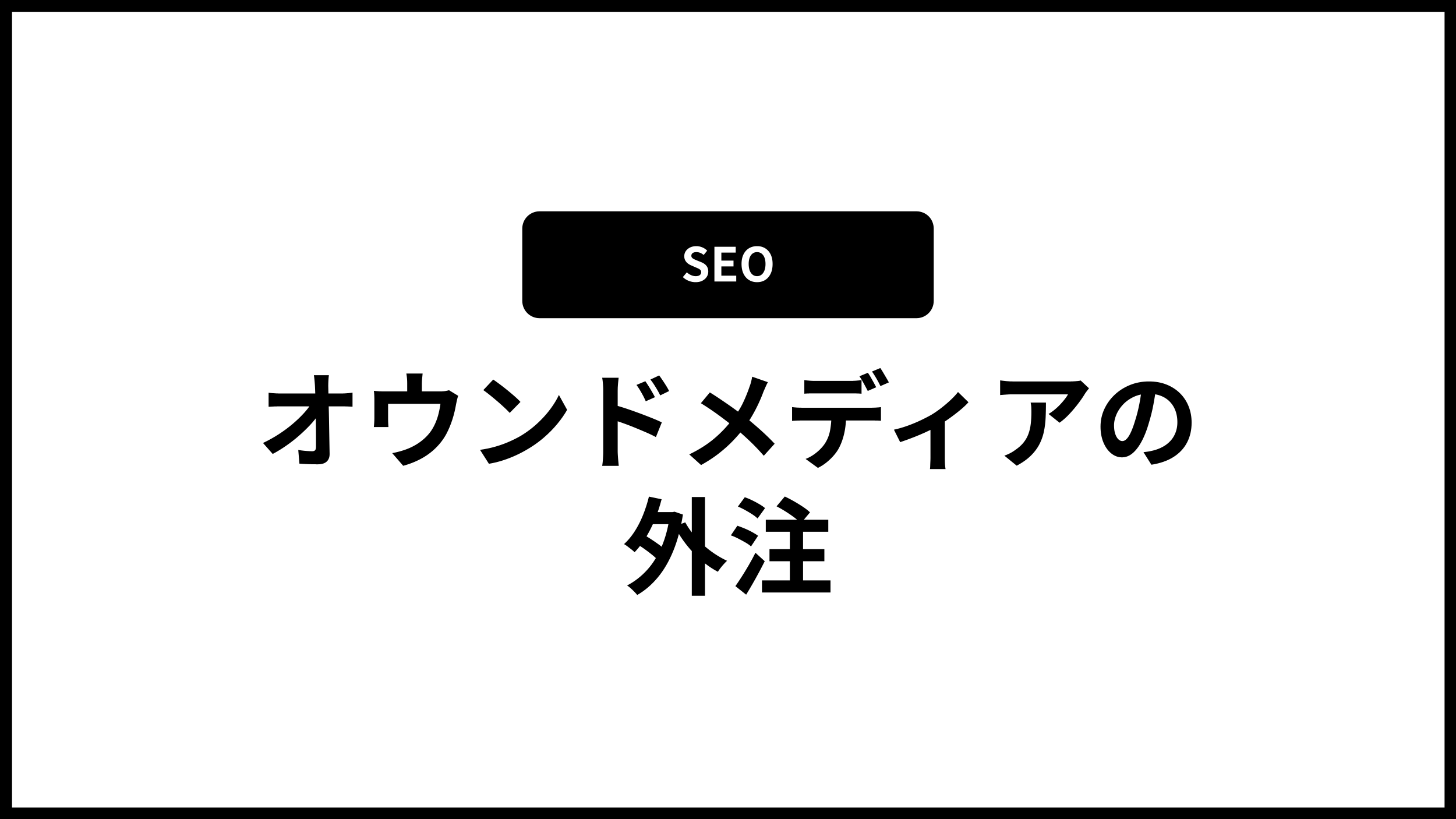
- オウンドメディアを始めたいが、社内に専門知識が不足しており、外注の選択肢を模索中。
- オウンドメディアを運営しているが、記事の更新が追いつかず、クオリティも低下しているため、外注を考えている。
- オウンドメディアを外注しているが、品質が低くてなかなか記事を公開できない。
上記のような課題を抱えている企業のために、本記事ではオウンドメディアの外注について、費用相場やメリット・デメリット、成功のポイントから失敗例までを実体験を交えて解説します。
外注によってコンテンツマーケティングを加速させ、成果を上げている企業の事例も交えつつ、
- オウンドメディアの外注コストの目安(記事制作費用は数万円~、SEOコンサルは月額10~30万円程度など)
- オウンドメディアの外注先の選び方
- オウンドメディアの外注で失敗しないためのポイント
を紹介します。
この記事を読むことで、オウンドメディアの外注を成功させ、自社に合った外注活用法を見つけるヒントが得られるでしょう。
オウンドメディア外注のメリット
オウンドメディアの運営を外部に委託することには、多くのメリットがあります。
入稿記事数・リライト記事数を増やせるため、立ち上がりが早い
オウンドメディアの記事執筆や既存記事のリライト作業を一部アウトソースすることで、記事の公開本数を大幅に増やすことが可能です。
社内で兼任の担当者が記事を書いている場合、どうしても制作できる本数に限りがありますが、外注を活用すればコストをかけて短期間に多数の記事を作成できます。
記事公開の頻度が上がれば、オウンドメディア施策のPDCAサイクルを早く回せるため、効果が現れるスピードも早まるとされています
外注により記事数を増やせることは、オウンドメディアのアクセス増加やSEO効果の発現を加速させる大きなメリットです。
オウンドメディア担当者の金銭的・労力的なリソースを削減できる
記事執筆や校正にかかる時間を外注ライターや編集者に任せることで、社内担当者の工数を削減できます。
その分、オウンドメディア担当者はコンテンツの品質を担保する仕組みづくりや、効果測定・分析、ホワイトペーパーなど一次情報をまとめた資料作成といったより戦略的な業務に集中できます。
また、記事執筆にかかる人件費や教育コストの削減にもつながります。
確かに、完全内製するよりはSEOのコンサルティングフィーや記事作成の費用は外注すると上がります。
一方で、外注なら以下のコストを省けるため、採用関連のコストも抑えられるでしょう。
- 自社でライターを新規採用するコスト:採用担当を1名おく人件費
- 自社でライターを育成するコスト:社内のディレクターの人件費+工数
- 採用媒体の費用:Wantedlyやクラウドワークスなど。正社員の場合は転職エージェントなどの成果報酬
さらに、オウンドメディア運営以外のマーケティング施策(例えばWeb広告やイベント施策など)に社内リソースを振り向ける余裕も生まれます。本来注力すべきコア業務に専念できる点は、外注の大きなメリットと言えます。
プロによる高品質なコンテンツ制作が可能
外注を活用すれば、自社ではなかなか採用・確保できない優秀なライターや編集者に記事制作を依頼できます。
専門性の高い分野の記事であっても、その分野に詳しいプロフェッショナルに執筆を任せられるため、内容の濃い高品質な記事が期待できます。
また、オウンドメディアの記事外注では社内にない社外ノウハウを活用できるメリットがあるとされています
記事制作専門の企業であれば、ライターアサインから校正体制までオペレーションが整っているケースも多く、安定した品質の記事を供給してくれるでしょう。また、最新のSEO知見や業界動向についても、外注先のプロから教えてもらえる可能性があります。
自社スタッフだけでは難しい高品質かつSEOに強いコンテンツを継続的に生み出せる点は、外注する大きな価値と言えます。
メディア運営のリソースを変動費化できる
ここからはかなり経営的な話をします。
オウンドメディアを内製で本格運用しようとすると、専任の正社員ライターや編集者を採用する必要があり、人件費という固定費が発生します。
一方、業務委託による外注であれば記事単位やプロジェクト単位での契約が可能なため、コンテンツ制作コストを変動費化できます。
なぜ変動費化した方がよいか?それはオウンドメディアは成果が出るまでかなり不安定な性質を持つ媒体だからです。
Googleのコアアルゴリズムアップデートでの影響で、検索順位が一気に落ちて、1ヶ月で流入が90%減少、といったことも起こり得るのです。
このような場合に複数名の正社員をチームとして採用していたら… 配置転換なども検討しなければなりませんし、さまざまな労務リスクを負うことになります。
外注なら状況に応じて発注数を増減する柔軟性があります。オウンドメディアは必ずしも100%成果が保証できる施策ではないため、経営目線では可能な限り固定費を減らし、リスクを抑えることが重要です。
オウンドメディア外注のデメリット
メリットの多いオウンドメディア外注ですが、検討にあたって把握しておくべきデメリットや課題も存在します。
外部に任せることで発生するコスト増や、自社ならではの色を出しにくい点など、事前に知っておくべき注意点があります。
ここでは、オウンドメディアを外注する際の代表的なデメリットと、その対策について解説します。
インハウスで運用するよりも費用がかかるケースがある
外注を利用すると当然追加の費用が発生します。
完全に自社内だけで運営する場合と比べ、
- 記事制作の発注費用
- ディレクション費用
など、外注先への支払いが必要です。
特に記事制作代行会社に依頼する場合、提示される文字単価や記事単価には代理店のマージンも含まれるため、一記事あたりの原価は内製より高くなりがちです。
例えば、代理店経由で1文字5円の単価で発注している場合、実際にライター本人には2~2.5円程度で発注し、残りが代理店の取り分となっているケースもあります。
そのため、同じライターに直接依頼できればもっと安く済む計算になり、外注に出すことで割高になる部分があるのは否めません。
さらに、記事本数が増えるほど総コストも増加し、外注に頼りきりだと継続的に費用がかかり続けるという指摘もあります。
また、オウンドメディアを外注任せにして社内にノウハウが蓄積されない状態になると、将来的にも外注し続けざるを得ず、費用も継続発生する悪循環に陥る可能性があります。
コストを抑えるためには、自社で対応できる部分は内製し、足りない部分のみ外注するなどの工夫も必要でしょう。いずれにせよ、インハウス運用と比較して割高になる費用面は外注のデメリットの一つです。
コンテンツの一貫性を保つのが難しい
外部のライターや制作会社にコンテンツ制作を任せる場合、自社ならではの独自性やメッセージの一貫性を維持することが難しくなる場合があります。
外注先はコンテンツ制作のプロではありますが、自社のサービスや業界に対する深い知識・理解を持っているわけではありません。そのため、どうしても記事内容が自社独自のカラーや強みを十分に反映しにくくなる傾向があります。
特に、自社製品・サービスの微妙なニュアンスや企業としてのスタンスなど、内部の人間にしか分からない要素は、外注スタッフだけでは汲み取りにくいでしょう。
この問題への対処法としては、外注先との丁寧な情報共有とコミュニケーションが欠かせません。
事前のヒアリングを綿密に行い、自社の業界知識や提供したい価値観を可能な限り共有することが重要です。それでも限界はあるため、外注先任せにするのではなく、社内で最終チェックを行うフローを組み込み、トーン&マナーの統一や事実関係の検証は社内でも実施すると安心です。
コンテンツの一貫性を保つには、外注利用時でも社内側の関与が必要だと認識しておきましょう。
外注先選びに時間がかかる
優れたオウンドメディア運用代行先や記事制作パートナーを見つけるのは簡単ではありません。
コンテンツ制作やSEOに詳しい外注先を探し出すには時間と労力がかかる場合が多く、特に外注自体が初めてで「どのように選べばよいかわからない」という場合は、複数社に声をかけて比較検討(相見積もり)するプロセスが必要になります。
外注先の候補探しから問い合わせ、打ち合わせの日程調整、提案内容の比較など、パートナー選定には意外と手間がかかるでしょう。
また、外注を利用する場合、依頼後も外注先とのコミュニケーションや進行管理にある程度の時間を割く必要があります。
記事の意図を正しく伝えるすり合わせやフィードバックのやり取りなど、コミュニケーション量はゼロにはなりません。
実際、記事外注では「外注先との連絡や管理に時間を割く必要がある」点を見落としがちです。
このように、信頼できる外注先を見極めることと、その後のコミュニケーションも含めて、時間と手間がかかる点はデメリットと言えるでしょう。
オウンドメディアにおける外注業務の範囲
オウンドメディア運営には様々な工程がありますが、その多くの部分で外注が可能です。
記事コンテンツの制作部分だけでなく、戦略設計から効果測定まで、専門知識を要する領域を外部に委託することで、効率的かつ効果的な運用が期待できます。
ここでは、オウンドメディア運営において外注できる主な業務の範囲を説明します。
戦略設計やテーマ決定
オウンドメディアを成功させるには、闇雲に記事を量産するのではなく、明確な戦略設計のもとで運用することが重要です。
外注先の中には、コンテンツマーケティングの戦略立案からサポートしてくれる会社もあります。
具体的には、
- 自社プロダクト・サービスの強み分析
- 自社ドメイン(サイト)の現状評価
- 競合サイトの調査
- 市場環境の把握
などを通じて、どの領域・テーマに注力すべきかを決めるステップです。
オウンドメディアの専門業者であれば、様々な業界のメディア運用実績があるため、客観的な視点で「狙うべきテーマ」「訴求すべきポイント」のアドバイスをしてくれるでしょう。
戦略部分をプロに任せることで、初期段階から効果を最大化しやすい土台を築くことができます。
キーワード選定とコンテンツ企画
オウンドメディアの命ともいえるキーワード選定や記事の企画立案も、外注可能な業務範囲です。
SEOの観点で適切なキーワードを選ぶには、ユーザーの検索ニーズを分析しつつ競合状況も踏まえる必要があります。
経験豊富な外注先であれば、無数のキーワード候補から適切な検索キーワードを抽出し、それに基づいたコンテンツ企画を提案してくれます。
たとえば、「競合が少なめで需要のあるキーワード」を見つけ出し、そのキーワードで上位表示を狙う記事テーマやタイトル案を作成するといった流れです。
どのような記事テーマが読者の関心を引き、ビジネス目標につながるかといったコンテンツ企画立案も外注先に任せることで、効率的に質の高いコンテンツ計画を策定できます。
記事の構成案作成とライティング
実際の記事執筆プロセスも外注の中心となる部分です。
まず、SEOで上位表示を狙うために重要な記事構成案(アウトライン)の作成があります。
外注先の編集者やSEOライターが、選定キーワードで競合上位の記事を調査し、見出し構成や盛り込むべき内容の案を作成します。
構成案について依頼主の確認を経て問題なければ、プロのライターが実際のライティングを担当します。
専門性の高い分野の記事でも、該当分野に詳しいライターが執筆することで質の高いコンテンツに仕上がります。
もちろん初稿後の修正対応も外注範囲に含めることができ、納得のいく形になるまで手直しを依頼できます。
自社の事情で記事を書く時間が取れない場合や、文章のプロに任せたい場合には、この構成作成〜執筆の工程を丸ごと外注することで高品質な記事を効率よく生み出すことが可能です。
校正/校閲
記事の内容に誤りがないか確認したり、読みやすい表現になっているかチェックしたりする校正・校閲作業も外注できます。
記事数が多くなってくると、一つひとつの文章を細かくチェックするのは社内では大変です。そこで編集プロダクションや校正専門者に依頼すれば、事実関係のチェックや日本語表現の統一、誤字脱字の修正などを徹底して行ってもらえます。
特に専門的な記事の場合、内容の正確性を確保するためにダブルチェック体制を敷くことが重要です。
外注先に校正・校閲まで任せることで、コンテンツの信頼性を高めつつ、社内担当者の確認作業負荷を減らせます。
ただし、自社で定めたブランド用語の使い方や業界特有の言い回しなどがある場合は、事前にガイドラインを共有し、外注スタッフと認識を合わせておくことが必要です。
効果測定の実施
記事を公開して終わりではなく、その後の効果測定や改善提案まで含めて外注できるケースもあります。
具体的には、
- 検索順位のモニタリング
- オーガニック流入数の分析
- 滞在時間・直帰率などのウェブ解析
- コンバージョン計測
などを継続的に行い、オウンドメディア施策の効果を評価します。
さらに、分析結果を踏まえた改善施策の提案(「どのページをリライトすべきか」「新たに狙うべきキーワードは何か」等)も含めてレポーティングしてくれる外注サービスもあります。
こうした効果測定・レポート作成まで委託すれば、社内でデータを解析するリソースがない場合でもPDCAを回しやすくなります。
もちろん、自社と外注先で定例MTGを実施し、数字を共有しながら次の一手を相談していく形が望ましいです。
外注で得た結果データをしっかり活用できれば、より戦略的なオウンドメディア運営が実現するでしょう。
外部対策の依頼
オウンドメディアで流入を増やすためには、コンテンツを入稿するのみではなく、外部対策が必要不可欠です。外部対策とは、外部のサイトから被リンクを獲得したり、サイテーションを獲得するための施策となります。
サイト自体のリンクが弱い場合は、必ず必要な施策になってきますが、優先度は企業によって異なります。そのため、オウンドメディアを外注する際に、ぜひ専門家に外部対策の必要性についても確認してみるとよいでしょう。
参考)SEOの外部対策とは?実践的な方法を解説【DR54まであげた経験談】
オウンドメディア外注の費用相場
オウンドメディアを外注する場合、具体的にどれくらいの費用がかかるのか気になるところです。
依頼する内容や範囲によって金額は大きく異なりますが、ここでは代表的なサービスごとの費用相場を解説します。記事単体の制作費からコンサルティング費用、サイト構築費用まで、おおよその目安を把握しておきましょう。
記事制作だけの外注費用
オウンドメディアの記事執筆業務だけを外注する場合、1記事あたり1.5万円~10万円程度が一つの目安になります。
費用幅が大きいのは、記事の長さや専門性、品質レベルによって単価が変動するためです。
一般的なWebライターへの報酬相場は1文字あたり約1~5円程度とされており、専門性や難易度が上がるとそれ以上の単価になることもあります
例えば、比較的易しい内容で3,000文字の記事なら1記事あたり3,000~5,000円程度で請け負うケースもありますが、医療や法律など高度な知識を要する記事では1記事あたり数万円以上の料金になる例もあります。
実際、フリーランスのライターへ直接依頼する場合は私の経験だと、文字単価は以下のようになります。
- 専門性が不要な記事:〜1円(観光, ゲーム)
- ある程度専門性が必要だが、供給が多い分野の記事:〜2円(キャリアなど)
- 専門性が必要だが、供給が少ない分野の記事:〜5円(医療 / 法律 / 金融など)
仮に文字単価2円で5,000文字の記事の場合、ライターへの支払いは1記事1万円程度です。
一方で、外注会社に依頼する場合、外注会社にマージンが入ります。マージン比率は30%-50%くらいまでとるケースが多いので、純粋1.3〜1.5倍の文字単価になります。そのため、例えば仮に文字単価4円で10,000文字, マージン率50%と仮定すると、
- ライターさん:文字単価2円, 報酬2円 * 10,000文字 = 20,000円
といった金額感になります。
なお一般的に記事制作会社ではマージン率は開示していないことがほとんどですし、聞いてもおそらく教えてくれません。
SEOコンサルティング費用
オウンドメディア運営を包括的にサポートしてもらうSEOコンサルティングの費用は、月額10~30万円程度が一つの目安です。
契約内容にもよりますが、この範囲であれば中小企業向けのコンサルティング料金帯に相当します。
この金額で、
・定例ミーティングやチャットでの質問対応
・コンテンツ戦略の提案
・検索順位レポート提供
などを毎月受けられるケースが多いです。
コンサル会社によっては最新のSEOニュース提供や社内勉強会の実施など付加サービスが含まれる場合もあります。
なお、対象が大規模サイトの場合や、サービス範囲がサイト改修・技術的SEOまで及ぶ場合は月額50万円以上の高額になることもあります
基本的には、企業の規模や目標に応じてコンサル費用も上下しますので、見積もりを複数取って費用対効果を吟味するとよいでしょう。
オウンドメディア構築費用
オウンドメディアサイトそのものを新規に立ち上げる場合の初期構築費用は、依頼内容によって10万~100万円以上と幅があります。
たとえば、WordPressなど既存のCMSを使い既製のテンプレートデザインで構築する場合、数万円~十数万円程度の比較的安価な費用で済むことがあります。
一方で、デザインをオリジナルで起こしたり、多数のページや特殊な機能を盛り込んだりすると数十万円以上のコストがかかります。
オウンドメディア外注先の選び方
オウンドメディアの外注を成功させるには、信頼できる外注先を選ぶことが不可欠です。
外注先のスキルや相性次第で成果が大きく変わるため、慎重に選定しましょう。ここでは、外注先選びで注目すべきポイントを解説します。
実績や評判を重視する
まず重視したいのが、外注候補の過去の実績や評判です。同じ業界や似たターゲット層のオウンドメディア支援実績が豊富な会社であれば、こちらのニーズを理解して成果を出してくれる可能性が高まります。
外注先のホームページや資料で導入事例を確認し、自社に近いケースでどのような成果を上げたかをチェックしてみましょう。
過去に制作した記事のクオリティや上位表示実績などを見れば、提案内容の信頼性も判断しやすくなります。
ちなみに知り合いにSEOの代理店で働いている人がいたら、ぜひ聞いてみてください。コンペなどでいろいろ話を知っていることがあると思いますので。他社で炎上したプロジェクトからリプレイスで案件が来ているなど、代理店間の中の情報などももしかしたら聞けるかもしれません。
サービスの金額を確認
外注先によって提供サービスの料金帯は様々です。
大企業案件を主に手がけている大手SEO代理店やWeb制作会社の場合、提案内容は充実していても費用も高めになる傾向があります。
一方、中小企業向けにリーズナブルなプランを持つ会社もあります。
あらかじめ自社の予算感に合った価格帯の外注先を探すことも大切です。
例えば、フリーランスに個別に依頼する場合は代理店マージンがないぶん単価は抑えられますが、管理コストや品質のばらつきリスクが高まります。
逆に総合代行企業に頼む場合は費用は上がりますが、その分ディレクション込みで任せられる安心感があります。
企業 vs フリーランス、年間契約 vs 月単位契約といった違いによってもコスト構造が異なりますので、各社から見積もりを取り費用とサービス内容のバランスを比較検討しましょう。価格だけにとらわれず、その費用で何をしてくれるのか(含まれるサービス範囲)を確認することがポイントです。
ちなみに、小規模で担当者が明確に決まっているような代理店であれば、人材選定のリスクはある程度減らせると思います。
オウンドメディア運用会社の提供するサービス内容の確認
外注先ごとに、提供しているサービス領域や強みは異なります。
記事作成のみ対応というライティング専門会社もあれば、サイト構築やUIデザイン、コンバージョン率改善(CVR改善)、被リンク獲得、SNS運用、広告運用まで幅広くサポートする会社もあります。
自社が本当に必要としているソリューションを提供できる相手かどうか、事前に確認しましょう。
例えば、SEO施策全般を任せたいのにコンテンツ制作しかプランに含まれない会社だと物足りないですし、逆にコンテンツ制作だけお願いしたいのに余計な広告提案ばかりされても困ります。
特定のソリューションしか持たない会社の場合、自社には不要な施策でもそのソリューションを売るための提案をしてくる可能性もあります。
打ち合わせ時に感じた提案内容が自社の課題にマッチしているかを見極め、「この会社はどこが得意分野なのか」「提供サービスの範囲はどこまでか」を明確に把握しておきましょう。
必要に応じて「この部分だけお願いしたい」という相談に柔軟に応じてくれるかどうかもポイントです。
組織の強み
外注先企業自身の組織的な強みにも注目しましょう。具体的には、「その会社はSEOに本当に強いのか」「コンテンツのプロフェッショナル集団か」を見定めることです。
例えば、自社で運営しているオウンドメディアが検索上位に多数ランクインしている会社であれば、実力がうかがえます。
また、会社の創業者や主要メンバーが過去に大きなメディア事業を成功させた経験がある、などのストーリーも参考になります。導入事例を多角的に見て、その会社全体としての総合力を評価すると良いでしょう。
加えて、担当者個人の実力も見逃せません。
規模の大きな代行会社では営業担当は優秀でも、実際に自社案件を担当するディレクターやライターのスキルが低い場合があります。SEOのコンサルティング業界では、営業担当とコンサル担当が別のケースもあり、営業が無理を言って受注してきた案件を、到底叶えられないと思いながらコンサル側が疲弊しているケースも多々あります。
極端なケースでは「営業は経験豊富なSEOコンサルだが、配属された担当者は駆け出しライター同然」ということもありえます。
ですから、会社としての実績だけでなく、自社案件にアサインされるチームの質や、組織全体で品質が均質化されているかも確認しましょう。
初回打ち合わせの段階で担当予定者が同席するなら、その人の知見レベルや提案力をチェックすることをおすすめします。
総じて、会社と担当者双方の強みを見極め、信頼できる体制かどうか判断することが重要です。
コミュニケーション力と提案力の強み
外注先との関係構築では、コミュニケーションの円滑さと適切な提案ができるかが鍵となります。
こちらの課題や目的を話した際に、相手が的確に理解し建設的な提案をしてくれるかどうかは重要な評価ポイントです。
事業への解像度が高く、こちらの話を踏まえて有益なアイデアを出してくれる担当者であれば、協力してプロジェクトを進めやすいでしょう。
逆に、こちらの要望をあまり聞かず自社の売りたいメニューばかり押してくるようでは困ります。
また、対応のスピードや丁寧さも見ておきましょう。
問い合わせに対する返答が迅速か、コミュニケーションがスムーズかといった点です。コミュニケーションスタイルの相性も大切で、担当者と話しづらい・噛み合わないようでは後々ストレスになる可能性があります。
さらに、将来的に記事数を増やしたいなどリソースの増減に柔軟に対応できるかも確認ポイントです。
なお、迷った場合はテスト的に小規模発注をしてみるのも有効です。
可能であれば1記事だけ試しに依頼してみて、納品物の品質やレスポンスの速さ、提案内容などを総合的に確認するとよいでしょう。企業によってはテストライティングに対応しているケースもあります。
オウンドメディアを外注する際の組織パターンの特徴とよくある失敗例
オウンドメディアの外注運営には、社内外のリソース配分によっていくつかの組織パターンがあります。
それぞれの体制にはメリット・デメリットがあり、失敗しがちなポイントも異なります。ここでは、代表的な組織パターンとその特徴、また筆者の実体験や見聞きしたよくある失敗例を紹介します。
社内担当者ディレクター + クラウドワーカーなどのフリーランスで運営→ コストを抑えに行くならこれが一番良い
まず一つ目は、社内のコンテンツ担当者(ディレクター)が外注ライターを個別に採用・管理するパターンです。クラウドソーシングサイトなどを通じてフリーランスのライターを複数名契約し、社内ディレクターが記事テーマの指示出しや原稿チェックを行います。
この形態の最大のメリットは、コストを最小限に抑えられることです。
記事制作代行企業を介さないため中間マージンが発生せず、ライターへの支払い(文字単価など)だけで済みます。
そのため、予算に限りがある場合には非常に魅力的な選択肢です。実際、多くのアフィリエイトメディアや小規模オウンドメディアではこの運用が採用されており、最も低価格で外注体制を組める方法と言えます。
しかし一方で、社内ディレクターにかかる負荷が非常に大きくなりやすい点には注意が必要です。
ライターをクラウドソーシングで募ると玉石混交で、初心者からベテランまで様々な人が集まります。その中から良いライターを見極めて採用する採用コストがまずかかります。例えば、筆者が以前Wantedlyなどでライター募集をした際は、100人応募があって採用基準を満たす人は10人程度、実際に契約したのは5人ほどでした。
厳選したつもりでも、そのレベル感で文字単価2円前後の品質がようやく確保できる状態です。
応募者数を増やす工夫(例えばSNS上で積極的に募集告知をする等)をすれば多少質は向上しますが、それでも優秀な人材を採用するのは容易ではないと痛感しました。
さらに、複数のフリーランスから上がってくる記事の品質チェック(校正・校閲)やフィードバックもディレクターが担うため、記事本数が増えるほど社内担当者への皺寄せが大きくなります。
ライターによって文章力・知識レベルがばらつくため、校正ルールなどのオペレーション構築も自前で行わなければなりません。
こうした採用と品質管理という両輪を回す自信がある(もしくは社内に既にその仕組みやノウハウがある)場合は、この体制でも十分運用可能です。実際コストメリットは大きいため、うまく回せれば非常に効率の良い外注形態でしょう。
ただし、ディレクター1人に負荷が集中しすぎると途中で体制が維持できなくなる恐れもあるため、社内のリソース状況と照らし合わせて現実的かどうかを判断する必要があります。
社内担当者ディレクター + 記事制作会社 → 品質を最大化し、自社リソースを空けたいならこれが一番良い
次のパターンは、社内にディレクターは置きつつ、実際の記事制作や編集オペレーションを専門の制作会社に任せる形です。
社内のコンテンツ責任者がディレクション方針や成果物チェックだけ行い、ライターアサインや原稿の初期校正などは記事制作代行会社側で実施します。
こちらのメリットは、先ほどのフリーランス活用と比べて社内ディレクターの採用・育成負荷が軽減される点です。ライターの選定や教育、進行管理の大部分を記事制作会社が代行してくれるため、社内担当者はより上流の企画や戦略部分に集中できます。
ただし、納品される記事の品質は制作会社の力量に大きく依存します。
優秀な制作会社であれば的確なライターをアサインし、質の高い記事を上げてくれますが、そうでない場合は結局社内で手直しに追われることにもなりかねません。
結局のところ、外注先の選定眼がここでも問われます。
また、品質基準を共有するために校正ルールの言語化やトンマナの擦り合わせなど、制作会社とのコミュニケーションに労力を割く必要があります。外注先が変わればルールや好みの再説明も必要になるため、円滑に進めるためには成果物に対するフィードバックをマメに行い、徐々に共同で品質を作り上げていく意識が大切です。
費用面では、フリーランス内製型よりは原価が膨らみやすい点に留意しましょう。
制作会社が間に入る分マージン分コストアップしますが、採用やオンボーディング、管理コストを考えれば総合的に楽になるケースも多々あります。特にオウンドメディア代行会社が豊富なノウハウを持っている場合、むしろ外注した方が結果的に効率が良いこともあります。
社内に限られた人数で運営していて手が回らない場合や、コンテンツ制作の仕組みを早急に整えたい場合には、この社内ディレクター+記事制作会社の体制が現実的でおすすめです。
フル外注 クラウドワーカーなどのフリーランス ×→ ほぼ成功する可能性なし
オウンドメディア運営を完全に外注でまかなうパターンとして、社内の専任者を置かずにフリーランスに全工程を任せてしまう形が考えられます。しかし、筆者の経験上、フル外注を個人フリーランスのみで行って成功した例は見たことがありません。
これは強く断言できますが、このような体制はおすすめできません。理由はいくつかありますが、まず記事の品質に責任を持つ人が不在になりやすいことが挙げられます。
複数のフリーランスライターに書かせてそれを公開するだけでは、内容の整合性も担保しづらく、チェック機能が働かないため低品質な記事が量産されてしまう危険があります。誰も全体を統括していない状態では、投資した時間と費用が無駄になってしまうケースが非常に多いのです。
また、ライター個々人は組織ではないので、急な離脱や対応不能といったリスク管理も難しくなります。
基本的に成功率が極めて低い運用形態ですので、仮に予算が潤沢でないとしても社内ディレクションなしのフル外注(フリーランスのみ)は避けるべきです。
前述のように最低でも社内に品質管理や指示出しをする人を置く、もしくは信頼できるディレクター経験者を外部で雇うなどの工夫が必要です。稼働量も週3は最低とれる必要はあると思います。
フル外注 記事制作会社 △ → 運要素強め。ややリスキー。
もう一つは、オウンドメディア運営をすべて記事制作会社などに丸ごと任せてしまうパターンです。
戦略立案から記事企画、執筆、効果測定まで、すべてを代行会社に委ねる形になります。この場合、成功するかどうかは依頼先のオウンドメディア代行会社の質に大きく左右されます。実績豊富でコミット力の高い会社に当たれば、かなりの部分まで任せても成果が出るかもしれません。
しかし、筆者の経験では完全フル外注でうまくいっている企業はあまり見かけません。
やはり自社メディアの運営をすべて外部任せにすると、自社内にノウハウも残らず、成果が出なかったときの打開策も講じにくくなるためです。また、何も指摘ができないため、外注先に緊張感がなくなり、品質を上げようとする努力をしない場合に見逃す可能性があります。
基本的には、社内である程度オウンドメディア運営である程度チェックできる体制を作ったうえで、外注を使う方が望ましいでしょう。
最低限、記事の品質チェック(最終校閲)だけは社内でできるようにしておくと、コンテンツの大崩れを防げます。例えば「企画やキーワード選定は一緒に行う」「原稿は全て社内でも目を通す」など、部分的に社内コントロールを効かせる工夫がおすすめです。
それが難しい場合は、前述の社内ディレクター+外注チーム体制に切り替えることも検討すべきかもしれません。
高額な費用を投じてフル外注したのに成果が出ないという最悪の事態を避けるためにも、外注先任せにしすぎない仕組みを持つことが重要です。
オウンドメディアの記事外注の流れ
実際にオウンドメディアの記事外注を進める際には、どのような手順で進めるとスムーズでしょうか。ここでは、外注開始までの基本的な流れを説明します。事前準備をしっかり行い、複数の候補から最適な外注先を選ぶことで、外注効果を最大化することができます。
目標・課題・現状を軽く整理しておく
まず外注先を探す前に、自社の状況や目的を整理しておきましょう。以下の点をできる範囲で言語化しておくと、後のやり取りがスムーズになります。
- 何を実現したいのか:オウンドメディアを通じて達成したい目標を明確化します。例:「新製品の認知度向上」「問い合わせリードの獲得数増加」「専門分野でのブランディング確立」などです。
- 現状の課題は何か:現時点でオウンドメディア運営上どんな問題があるかを書き出します。例えば「社内のライティングリソース不足」「既存外注の品質が低い」「検索順位が思うように上がらない」「記事数が足りずPDCAが回せない」などです。
- ビジネス上の制約・与件:月〇本の記事が必要、予算は〇円まで、関連部署との調整事項、コンプライアンス上の注意点等、あれば整理します。
- 外注先に期待すること(例:「記事執筆だけでなくSEO戦略も含めてお願いしたい」「技術的な内容なので専門知識を持つ人に書いてほしい」等)
これらの情報を簡潔にまとめておけば、外注先との最初の打ち合わせ時にこちらの要望を正確に伝えられます。
目的や課題が曖昧なままだと、外注先からの提案も的外れになりかねません。逆に、こちらが必要としていることが明確であれば、外注先は事前に調査を行い効果的な対応方針を考えてきてくれるでしょう。
いくつかの与件を整理して、オウンドメディア運用代行企業に相見積もりを取る
自社の要件がまとまったら、それを持って複数の外注候補に問い合わせ・見積もり依頼をしてみましょう。
上で整理した情報をフォームのお問い合わせ欄にコピーしてそのまま伝える形で構いません。「御社に依頼する場合、どのような支援が可能で費用感はどれくらいか」といった形で問い合わせれば、多くの場合担当者との商談や提案を経て見積もりを提示してくれます。
最初から1社に絞る必要はなく、相見積もりを取ることで各社の特色や価格帯、またサービス品質を比較できます。
ポイントは、まともな会社であれば商談前にこちらの与件を踏まえてある程度リサーチや仮方針を用意してきてくれるということです。
例えばこちらのサイトを事前にチェックし、「◯◯のキーワードで伸びしろがありそう」「記事構成は△△のパターンにすると良い」など、初回の打ち合わせから有益な指摘や提案をもらえる会社は信頼できます。
逆にテンプレート的な営業トークばかりだと少し不安です。
初期商談の段階で親身に考えて頑張ってくれる会社を選ぶと、その後の伴走支援の質も高い傾向にあります。
オウンドメディア外注で失敗しないためのポイント(実体験と本音)
オウンドメディアの外注運用には様々な落とし穴も存在します。筆者自身の実体験や周囲の事例から学んだ、失敗しないための教訓をいくつか紹介します。同じ間違いを繰り返さないよう、ぜひ参考にしてください。
育成にリソースをとりすぎ失敗→フリーランス外注人材を利用するなら育成よりも採用に命をかける
外注ライターを使い始めた当初、筆者は「フィードバックを丁寧に行えばライターのレベルが上がっていくだろう」と考え、教育・育成に力を入れました。しかし結果から言うと、これは大きな失敗でした。特に文章力や論理的思考力といったものは、ある程度その人のベースで決まっており、いくら社内で校正してフィードバックしても劇的には伸びないものだと痛感しました。論理展開力などは大人になってから急激に向上するものではなく、いくらこちらが手間をかけても成果に結びつかないケースが多かったのです。
そこで発想を転換し、ライターの「育成」よりも「採用選考」にリソースを割くようにしました。多少大変でも、最初から優秀な人を厳しく選び抜いて採用することに注力したのです。その結果、驚くほどスムーズに品質の高い記事が上がってくるようになり、以前抱えていた悩みが一気に解消しました。実際、当社ではこれに気づくまでに約1年かかりましたが、優秀なライターさんを一人採用しただけで膨大だった修正・指導の手間がほぼ無くなりました。
この経験から学んだのは、外注ライター活用においては育成よりも最初の選定が命ということです。スキルの高い人に最初から頼めば済む話で、わざわざ低単価の人を雇って育て上げるコストは割に合いません。ですから、リソースに限りがある場合こそ「最初の採用(選抜)に全力を注ぐ」べきです。妥協せずできるだけ多くの候補者に当たり、時間をかけてでも良い人材を採用する方が、結果的に外注成功への近道となります。
面談に時間を割きすぎ失敗→外注ライターの採用はテストライティングがキー
ライター採用の際、当初は筆者も面談(インタビュー)で人物評価を重視していました。しかし、記事制作においては面接での印象より実際に書いてもらった文章の質こそが重要です。そこで途中から、採用フローに有償のテストライティングを導入するようにしました。これが功を奏し、採用の成否が劇的に改善したのです。
具体的には、実際に候補のライターさんに試しの記事を書いてもらうステップを設けました。テストライティングは無料では応募してもらえないこともあるため、謝礼をお支払いしています。当社では目安として3,000円程度を払い、2,000~3,000文字ほどの記事を1本執筆してもらいました。このテスト記事を書いてもらうことで、候補者の文章力・調査力・納期遵守などを実地で確認できます。面接だけで判断していた頃と比べ、テストライティングを経た採用では明らかに入ってくるライターの質が向上しました。面接では穏やかで論理的に話せていても、実際の執筆になると文章が冗長だったり要点がずれていたりする人も多く、やはり書いてみてもらわなければ分からないと痛感しています。
現在では、面談は最低限の意思疎通確認程度にして、テスト執筆の結果を最重視して採用を決めています。このように、ライター採用の鍵はテストライティングにあると思います。多少手間と費用は増えますが、最初に適切な選抜をすることで長期的な品質は大きく向上します。外注ライター選定で失敗しがちな場合は、ぜひテストライティングの導入を検討してみてください。
ライターの採用の失敗で、社内ディレクターに皺寄せがいき退職→育成よりも採用に命をかける
これは実際に当社で起きてしまった失敗なのですが、ライターの採用ミスにより社内のコンテンツディレクターに過度な負担がかかり、最終的にその担当者が退職してしまったことがありました。具体的には、当初採用した外注ライター陣のレベルが低く、納品されるコンテンツの品質が期待を下回るものばかりだったのです。社内ディレクターはまずライターたちに何度もフィードバックを行い修正を促しましたが、改善が見られない記事が多発しました。次第にディレクター自身が「一から自分で書き直した方が早い」と考えるようになり、納品記事を自ら大幅にリライト・修正する状況になっていきました。そして休日に隠れて修正タスクに追われ、体調を壊してしまいました。
最初は数記事であれば何とか対応できていましたが、これが10本、20本と積み重なるにつれ、ディレクターの工数は膨大になりました。毎日大量の文章修正に追われ、本来の企画や分析業務に手が回らないばかりか、休息時間も削られる状態です。結果、そのディレクターは心身ともに疲弊し、自社のオウンドメディア運営そのものに嫌気がさしてしまいました。最終的には転職という選択をされ、会社としても貴重な人材を失う痛手を負いました。
この失敗から明確になったのは、粗悪なライターの採用は社内にも大きな悪影響を及ぼすということです。低品質コンテンツが大量納品されると、それを捌く社内の人間が潰れてしまうのです。
改めて、良いライターを厳選して採用することが何より重要であり、多少お金をかけてでも最初から有能な人に頼むべきだと痛感しました。
このような悲劇を生まないためにも、「育成より採用に注力」という前述のポイントがいかに大事かが分かります。
外注ライター選びで妥協すると社内負荷が跳ね返ってくることを肝に銘じ、採用段階で手を抜かないようにしましょう。
外注先のライターがコンテンツの盗用を行っていた→チェック時にコピーコンテンツチェックの導入を検討
外注ライターによるコンテンツ盗用(コピペ)問題にも注意が必要です。これは当社ではなく、当社の知人の会社で実際にあったケースです。
発注していたフリーランスライターの一人が、他サイトの記事内容を無断流用してコンテンツを作成していたことがありました。発注元の企業側は納品された段階ではチェックせず公開してしまいました。しかし後になって、盗用されたサイト運営者から「自社の記事内容が流用されている」と指摘を受け、問題が発覚したのです。当然、発注側の経営者は不本意ながら謝罪と該当箇所の修正対応に追われ、大きな信頼低下には至らなかったものの冷や汗をかいたそうです。
このような盗用行為は悪質な場合もありますが、近年は生成AIの利用などによりライター本人が意図せず他コンテンツと類似度の高い文章を作ってしまうケースもあり得ます。いずれにせよ、コンテンツの一部でもコピーが含まれているとSEO上のリスクや法的なトラブルにつながる可能性があります。したがって、外注体制の中にコピーコンテンツチェックのプロセスを組み込むことを強く検討すべきです。具体的には、納品された原稿を受け取った段階で、コピペチェックツール(たとえばCopyContentDetectorやコピペリンなど)を使って他サイトからの流用がないか確認するフローを導入します。
不安な場合は、ライターへの発注ルールとして「AIでの自動生成や無断転載禁止」「参照元がある場合は必ず明記」などを明文化しておくと良いでしょう。チェック体制を整備することで、万一盗用が発生しても公開前に発見・対処でき、企業リスクを未然に防げます。
品質が担保されないまま大量のコンテンツがリリースされ、プロジェクトが炎上→品質チェックのためのガイドラインを整備
オウンドメディアの外注運用でありがちな失敗に、品質基準が曖昧なままコンテンツを量産してしまうケースがあります。
執筆ルールや期待するクオリティを明確にしないまま多数の記事が納品・公開されてしまうと、結果として「大量のゴミ記事」が出来上がる危険があります。そのままでは検索順位も上がらず成果も出ないため、「一体何のために費用をかけたのか…」といった最悪の事態になりかねません。あるいは、外注先から上がってきた低品質記事群を社内ディレクターが慌てて全部手直ししようとして疲弊する、といった炎上状態になることもあります。
こうした事態を避けるためには、外注開始前に品質チェックのための各種ガイドラインを整備しておくことが有効です。具体的には、以下のようなドキュメント類を用意しておくとよいでしょう。
- ブランドガイドライン:自社メディアのトンマナ(トーン&マナー)、言葉遣い、読者層、記事のねらいなどをまとめたもの。
- 執筆ガイドライン:記事構成や見出しの付け方、文体(です・ます調/だ・である調など)、専門用語の用字用語、句読点の使い方など文章作成上のルール。
- 校正ガイドライン:数字や固有名詞の扱い、表記ゆれの統一ルール、引用の仕方など、校正時にチェックすべきポイントの基準。
- 校閲ガイドライン:事実確認手順や裏付け情報の示し方、禁止事項(不確かな情報の記載禁止など)を定めたもの。
すべて完璧に用意するのは難しいかもしれませんが、可能な範囲で最低限の決まり事を書面化して共有しておくことが大切です。これがないまま個別に記事ごとに「ここは直して」「あそこも修正して」と何度もやり取りすると、外注先から「基準が分からずやりづらい」と不満が出たり、最悪「御社の対応にはついていけない」と契約打ち切りを告げられるケースすらあります。ガイドラインが明確に存在し、外注先が自主的にそれを基に校正を行える状態が理想です。そのため初期段階で手間を惜しまずガイドラインを整備・共有し、運用中も必要に応じてアップデートしていきましょう。
書いているコンテンツが他社の焼き直しばかり→独自情報が社内でまとまる仕組みづくり
外注ライターによる記事は、単価や時間の制約上、どうしてもネット上に既にある情報のまとめになりがちです。特に低~中単価で依頼している場合、深い独自取材や専門的分析までは望めず、結果として上位表示されている競合記事の内容をなぞったようなコンテンツになってしまうケースが非常に多いです。このままではオリジナリティに欠け、検索エンジンからもユーザーからも評価されにくいでしょう。
これを防ぐには、特定分野において専門性の高いライターの採用を行うか、独自の情報源やデータを外注ライターが活用できるように社内で提供する仕組みを作ることです。
例えば、
- 自社サービスの導入事例や成功ケースの具体的データ
- 市場動向に関する自社調査結果
- 専門家への簡易インタビュー内容
- 業界の専門家のリスト、および主要な参考文献
など、専門性をあげられるようなコンテンツを集積するスプレッドシートを作成しておきましょう。
そうすることで、外注ライターもそれらの一次情報を記事内で参照したり分析したりして、他サイトにはない切り口のコンテンツを書きやすくなります。
文字単価でやっていることが多いライターさんに「独自で徹底リサーチしてオリジナル情報を書け」というのは酷なため、社内から独自ネタを提供してあげるのがポイントです。
また、記事内でのCTA(Call To Action、行動喚起)も、社内でよく使うフレーズや売りとなるポイントを整理して共有しておくとよいです。例えば「お問い合わせはこちら」「無料資料ダウンロードはこちら」といった定型文や、訴求したい自社サービスの強みリストなどをあらかじめ外注チームに伝えておきます。
まとめておけば、外注側で記事内に自然に盛り込みCVR(コンバージョン率)を高める工夫をしてくれることが多いです。独自情報の提供に加えて、CTA周りの知見も共有することで、より効果的なコンテンツ制作が期待できます。
特定のオウンドメディア代行業者に依存しすぎて、コントロールできない→最悪自社でも運営できるように内製する仕組み作り
外注先に長く任せていると、その会社に依存しすぎてコントロールを失う危険もあります。
例えば、外注先が構築したオペレーションやノウハウがブラックボックス化しており、発注側の自社には全容が見えない状態だとしましょう。その状態で外注先から価格交渉で値上げを持ちかけられたりすると、代替手段がなく受け入れざるを得ない羽目になるかもしれません。
あるいは不満があって外注先を変えたいと思っても、自社にやり方が蓄積されていないために別の会社に切り替えるのが困難、ということもあり得ます。
このような状況を避けるため、将来的に自社内で運営できるように内製化の選択肢を残しておくことが重要です。
具体的には、外注先との契約期間中も定期的にプロセスの共有やノウハウの移転を図ることです。定例ミーティングで進捗報告を受けるだけでなく、
- どんなキーワード戦略でどう記事を作っているのか
- 使用ツールやチェック体制はどうなっているか
なども質問して把握しておきましょう。
できれば社内メンバーにも一部コンテンツ制作に携わらせ、外注先のやり方を吸収する機会を作ると良いです。外注先によっては内製化支援サービスを提供してくれるところもあります。
また、成果が出て順調に運営が軌道に乗ってきたら、徐々に社内チームに切り替えることも検討しましょう。
例えば外注での成功を踏まえて
- 社内ライターを新規採用する
- 編集者を育成する
といった具合です。
全部を完全に内製化する必要はありませんが、「本気を出せば自社でも回せる」という状態を目指しておくと、外注先に引きずられず健全な緊張感で付き合えます。
最悪外注を切り替える選択肢を持っておくことで、価格交渉の主導権もある程度こちらが握れるでしょう。
依存しきらない距離感を保ちながら、内製化の余地を残して外注運用するのが理想的です。
オウンドメディア代行業者に期待値が高すぎる→できること・できないことの期待値の擦り合わせが必須
最後に、発注側(依頼する企業)として外注先に対して過度な期待を抱きすぎないことも大切です。
オウンドメディア代行業者に任せれば全て魔法のように上手くいく、と考えるのは危険です。
なぜなら、外注先にも当然得意不得意があり、予算や契約範囲の中でできることには限界があるからです。
例えば、「記事を外注すれば勝手にSEOで上位表示されて問い合わせが増えるだろう」と丸投げすると、もし結果がすぐに出なかった場合に「話が違う」とトラブルになるかもしれません。
外注先としても、成功を保証できるわけではないですし、リスク/コストの高い提案(例えばドメイン移転や、プロダクトに深く関わるような大幅なリニューアル)などは避けて通るでしょう。
逆に発注側がどこまで関与すべきか、といった点を契約前によく話し合います。
また、「全部任せておけば良い感じにやってくれるだろう」という姿勢もよくありません。
外注先とは二人三脚で歩むものと考え、こちらも主体的に関わる姿勢が必要です。
例えば、記事のテーマ出しには自社の戦略や知見を共有する、内容のレビューにはフィードバックを欠かさない、といった関与はやはり発注側の責務でもあります。両者が歩み寄って協力することで、初めて理想的な成果が出ると心得ましょう。
要は、オウンドメディア代行業者も万能ではないので、お互いに現実的な期待値を設定し、役割分担を明確にした上でプロジェクトを進めるのが成功の鍵です。
できないことまで期待しすぎて失望することのないよう、契約時には目標KPIや具体的な対応範囲を文書で確認しておくと安心です。
発注側も受け身にならず積極的に意見を出し合い、協働する関係を築けば、理想的な運用に近づけるでしょう。
「オウンドメディアはすぐに成果が出ない」は半分本当で半分嘘
おそらく、オウンドメディアの運用代行を行なっている企業の営業担当やコンサルタントにこう聞いてみてください。
「オウンドメディアってすぐ成果出ますか?」
おそらく、「オウンドメディアはすぐに成果が出ない」と返ってくると思います。
これは半分本当で半分嘘です。
まず、当社でも同じようにう答えます。
しっかり説明すると、オウンドメディアですぐに成果が出る場合はこういうケースです。
- サイトのDRが70以上あり、超大手老舗サイトを運営している時。逆になんでこのタイミングになるまでオウンドメディアやってなかったのだ?と突っ込みたくなるような有名サイトがオウンドメディアを着手したいとき。社内調整は非常にスムーズで、スピード感もって仕事が進められる時。
- 経営者がSNSを死ぬほどリソース投下している時。フォロワーは3万人以上で、毎回相当な数のエンゲージメントがついている。オウンドメディアに対する優先順位が高く、書いた記事は経営者が全部シェアしてバズらせてくれるような協力体制がある時。
- いきなり年間予算1500万円以上をつぎ込んでくれる時。オウンドメディア以外の施策(SNS運用, SEO, 有料広告, テレビ広告、交通広告、PRなど)にも最高の人材をアサインして予算出してくれる時。
- 競合のデジタル施策が圧倒的に弱く、そのカテゴリで誰も露出していないような、競合環境の時。
当社でも例えば、SaaSプロダクトのデータベース型メディアを運営していますが、そこで作成したオウンドメディアは初月で100記事以上の検索順位1位を獲得しました。でもこれは、④競合環境が圧倒的に弱かったからです。

上以外のケースでは、
- 6ヶ月は無風
- 12ヶ月でようやく流入が増える
くらいを期待値として持っておくとよいです。
よくある質問(FAQ)
Q1. オウンドメディアの記事外注にはどれくらい費用がかかりますか?
A. 記事内容や依頼の仕方によって幅がありますが、目安として1記事あたり数万円(2~10万円程度)を見ておくと良いでしょう。
直接フリーランスに依頼する場合は文字単価3~5円前後が多く、3,000文字の記事なら数千円~1万円程度になります。記事制作代行会社に依頼するとディレクション費用込みで1記事5万円以上になるケースもあります。さらに専門性の高い記事では1記事数十万円規模の費用が発生することもあります。また、オウンドメディア運用全体を外注する場合、SEOコンサルティング費などで月額10~30万円程度かかることが一般的です。サイト構築費用は別途で、簡易なブログ構築なら10万円以下~、本格的なメディアサイトなら50~100万円超といった具合です。まずは依頼範囲を決め、複数社から見積もりを取って比較することをおすすめします。
Q2. オウンドメディアを外注するメリットは何ですか?
A. 主なメリットは以下のとおりです。
- 記事制作本数を増やせること:外注すれば短期間に多くのコンテンツを作成でき、サイトの成長を加速できます。
- 社内リソースの有効活用:記事執筆の手間を省き、社内の人員を企画や分析など他の重要業務に振り向けられます。
- 高品質コンテンツの確保:経験豊富なプロのライターや編集者の力を借りることで、自社では難しい専門性の高い記事や読みやすい記事を制作できます。
- 変動費化によるリスク低減:人を社内雇用せずに済むため、コンテンツ制作コストを必要な分だけに抑えられ、事業環境に応じて調整しやすくなります。
これらにより、自社だけで運営するより効率的かつ効果的にオウンドメディアを成長させられる点が外注のメリットです。
Q3. オウンドメディア外注のデメリットや注意点はありますか?
A. はい、いくつかあります。
まず費用面では、完全内製よりもコストが増える点です。記事数が増えるほど外注費用も嵩みます。またコンテンツの一貫性を保つのが難しく、外注先が自社の深い事情まで理解できないため独自色が出にくいことがあります。さらに、外注先とのコミュニケーションコストも発生します。意図を正しく伝えるすり合わせや品質チェックに社内側の時間も割く必要があります。そして、外注に頼りすぎると社内にノウハウが蓄積されない点にも注意です。長期的には外注先に依存してしまい、自社で運営できない状態になるリスクがあります。こうしたデメリットを軽減するために、費用対効果を常に検証しつつ、外注先とは密な情報共有を行い、社内でも知見を吸収する努力が重要です。
Q4. 信頼できるオウンドメディア外注先はどう選べばよいでしょうか?
A. 外注先選びでは次のポイントを確認するとよいでしょう。
- 過去実績の確認:同業界や似た規模のメディア支援実績が豊富か、成功事例があるかをチェックします。過去に制作した記事の質やSEO実績も見ましょう。
- 提案内容と担当者の相性:初期提案でこちらの課題に合った具体的なアイデアを出してくれるか、担当者が専門知識を持ちコミュニケーションが取りやすいかを評価します。
- サービス範囲と料金:自社が求める領域(記事執筆のみか、戦略やSEO全般か)をカバーしているか、料金は適正かを比較します。複数社の見積もりを取り、価格だけでなく内容を精査してください。
- 品質管理体制:ライターや編集の質をどう担保しているか、校正フローがあるか、納品後の修正対応はどうかなど、品質に関する取り組みも確認しましょう。
これらを総合して、「自社のパートナーとして信頼できるか」を判断することが大切です。迷う場合は少額の試し発注をして、納品物や対応を見てから決めるのも有効です。
Q5. オウンドメディア外注で失敗しないためには何に気をつけるべきですか?
A. いくつか重要なポイントがあります。
- 優秀な人材を採用する: 外注ライターやオウンドメディア代行業者の担当者の質が成否を分けます。安易に妥協せず、テストライティングなどを活用して優秀な人を選び抜きましょう。教育よりも最初の選抜が肝心です。
- 明確な基準を示す: 執筆ルールや品質基準を事前にガイドライン化し、外注チームと共有してください。基準がないまま進めると大量の修正や手戻りが発生します。
- チェック体制を整える: コピペチェックや事実確認など、納品物を検証するフローを社内側で用意しておきます。外注任せにせず、最終品質は自社でも確認しましょう。
- コミュニケーションを密に: 外注先との情報共有を怠らず、自社の独自情報やフィードバックは積極的に提供します。お互いに齟齬のないよう期待値を合わせ続けることが重要です。
- 内製化の目線を持つ: 外注に頼りきりにならず、将来的に自社でも運営できるようノウハウを蓄積しましょう。外注先への依存度を下げておくことで、柔軟な運用やリスク低減につながります。
これらに留意することで、外注のメリットを享受しつつ、失敗リスクを最小限に抑えることができます。特に「人」と「基準」と「連携」の3点が外注成功の鍵となります。